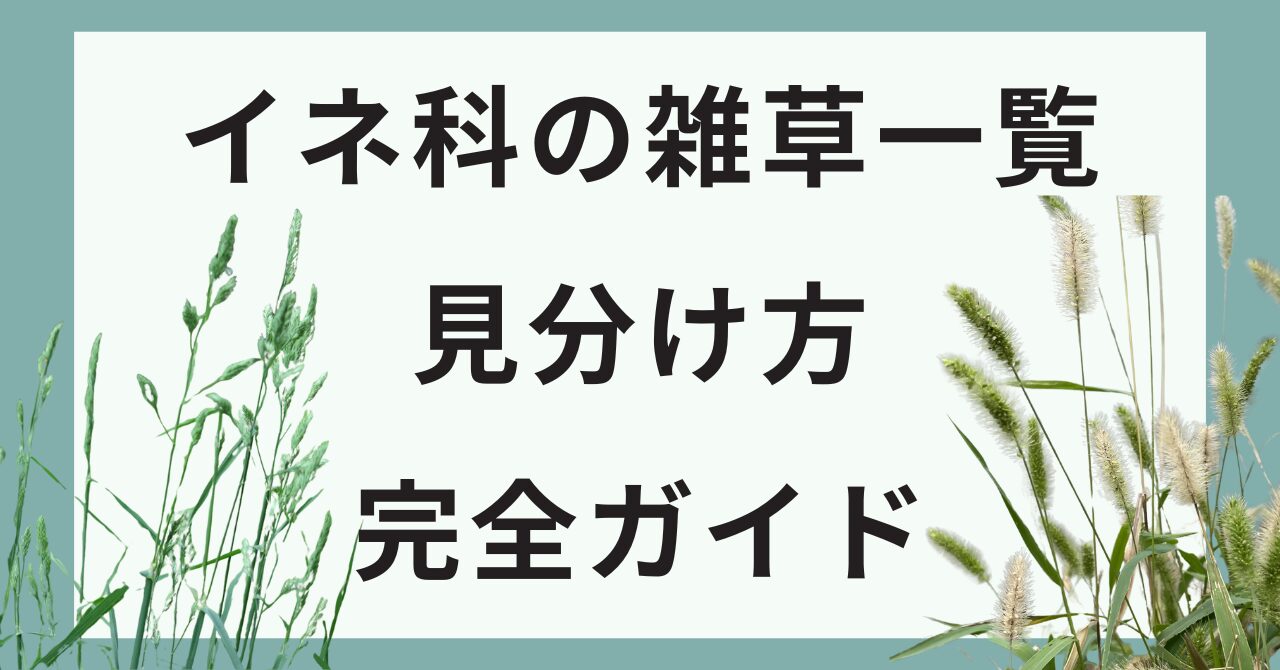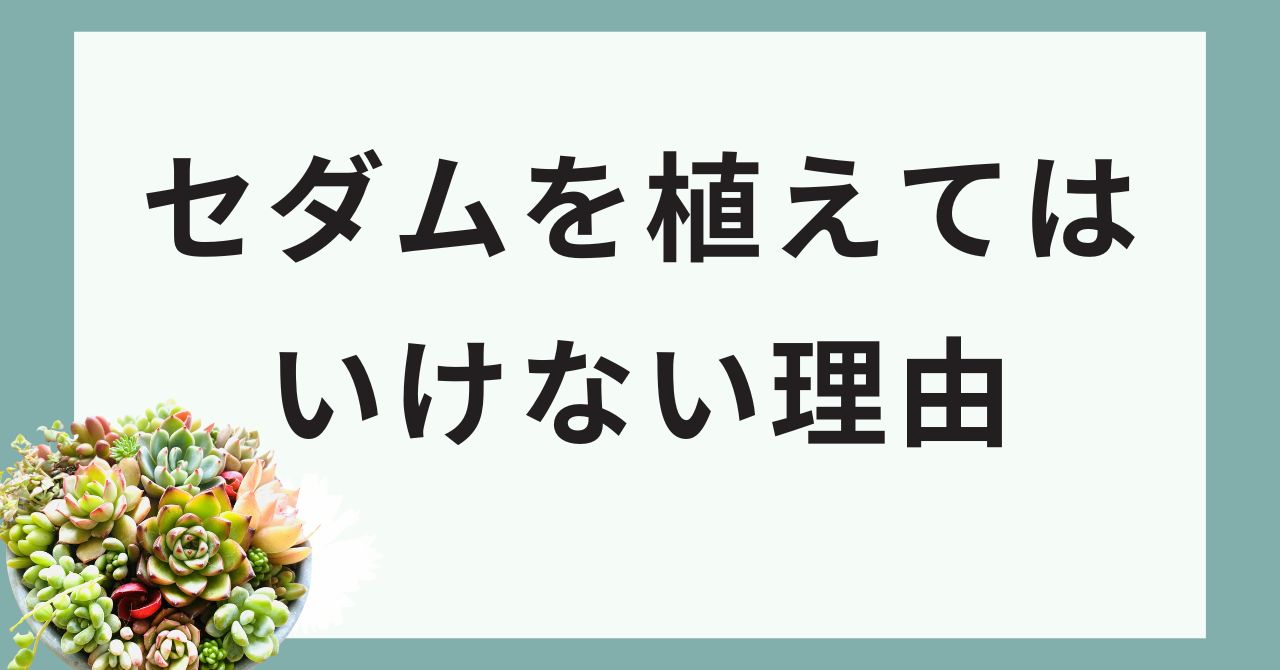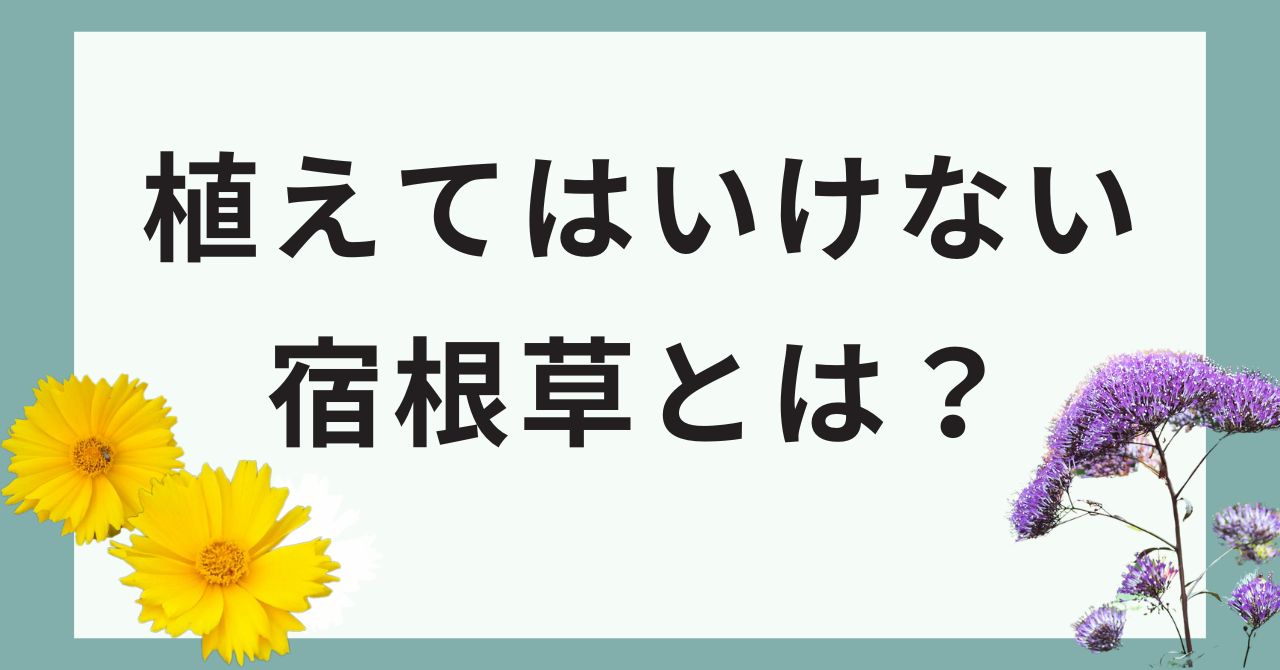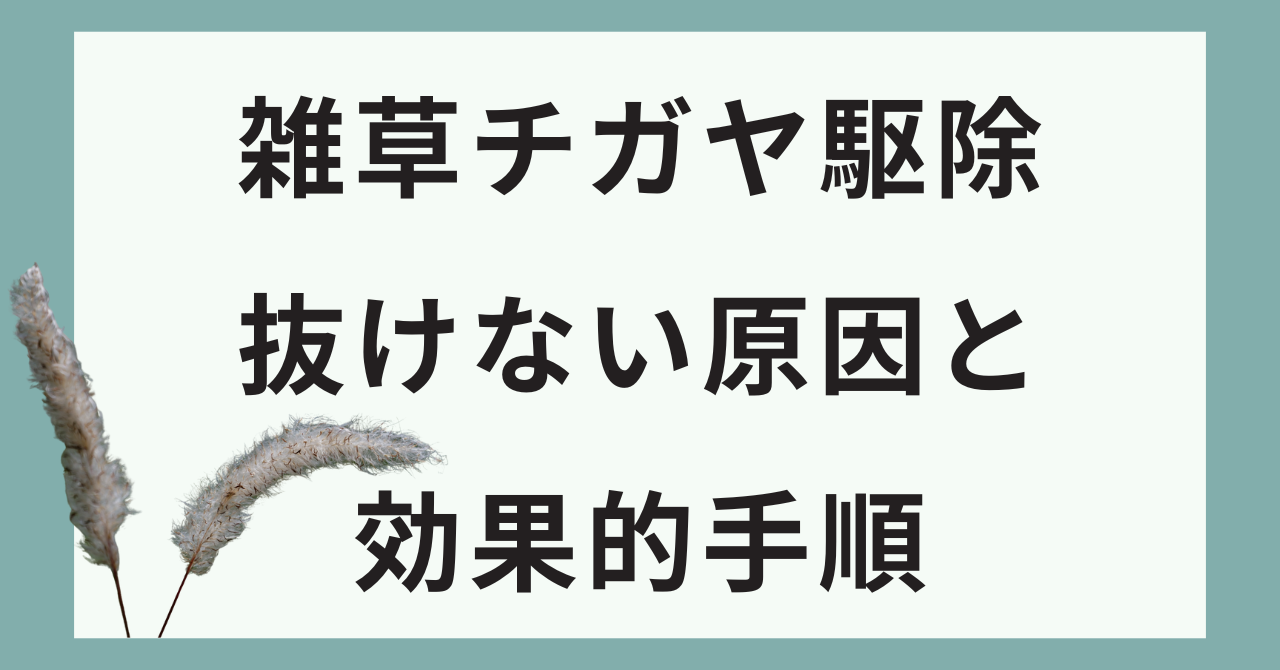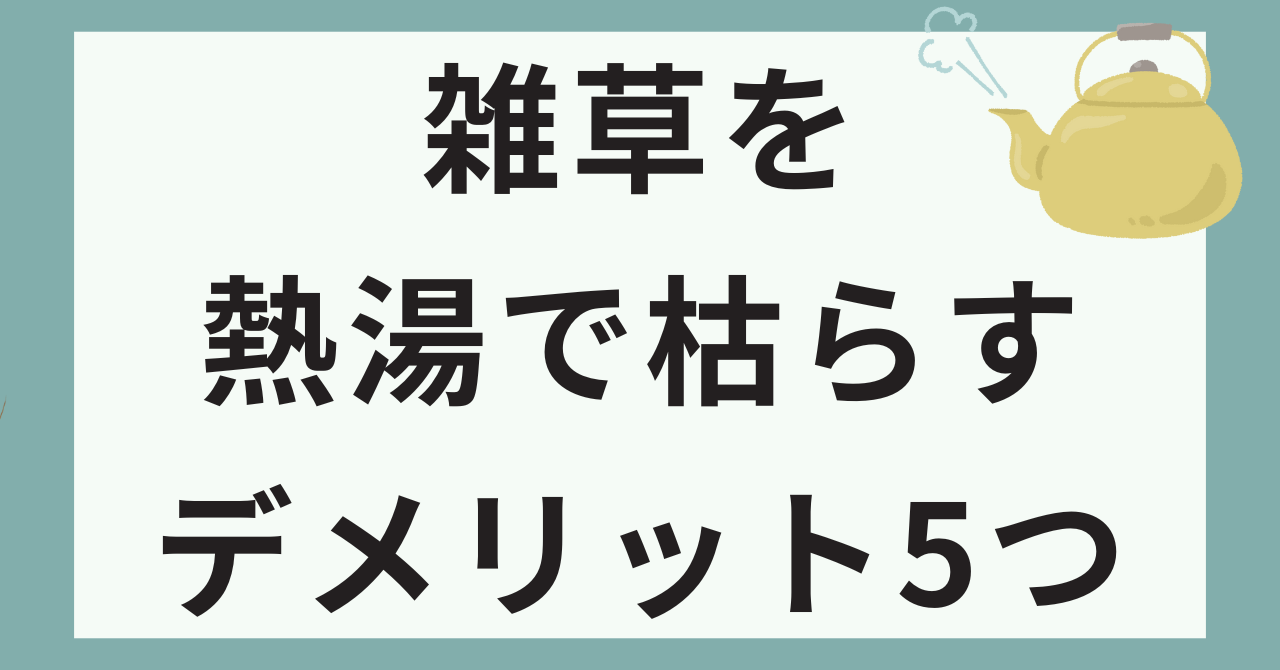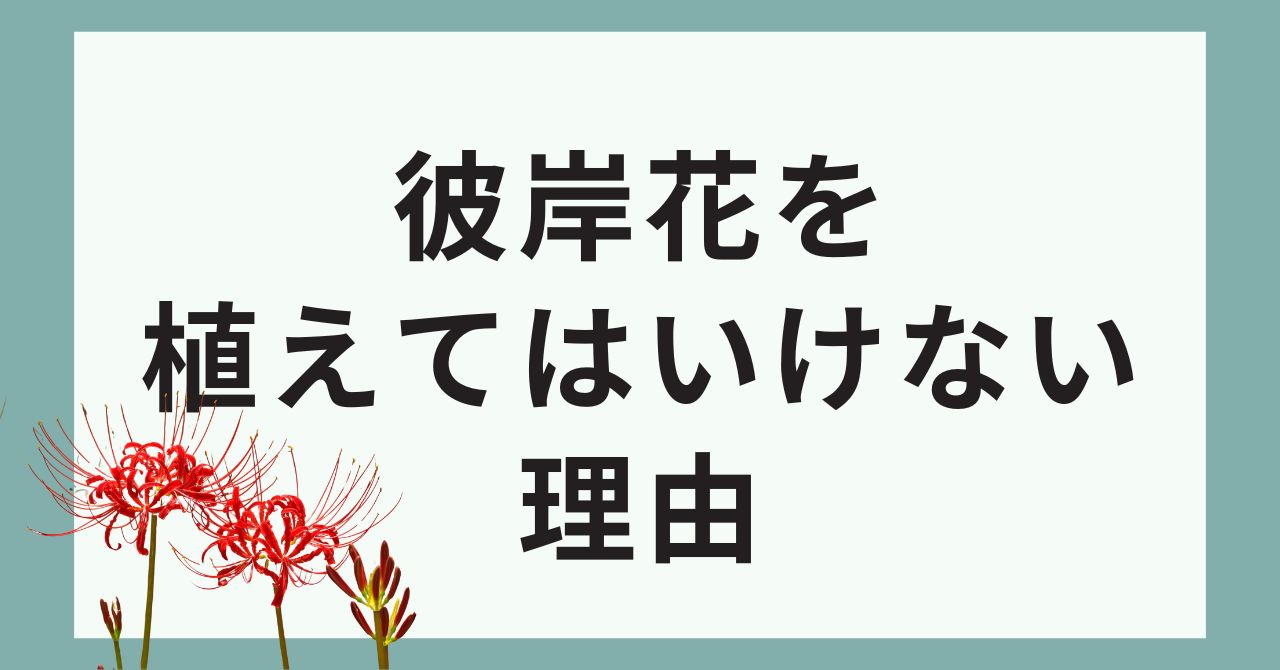黄色い花を咲かせる雑草の名前一覧&見分け方
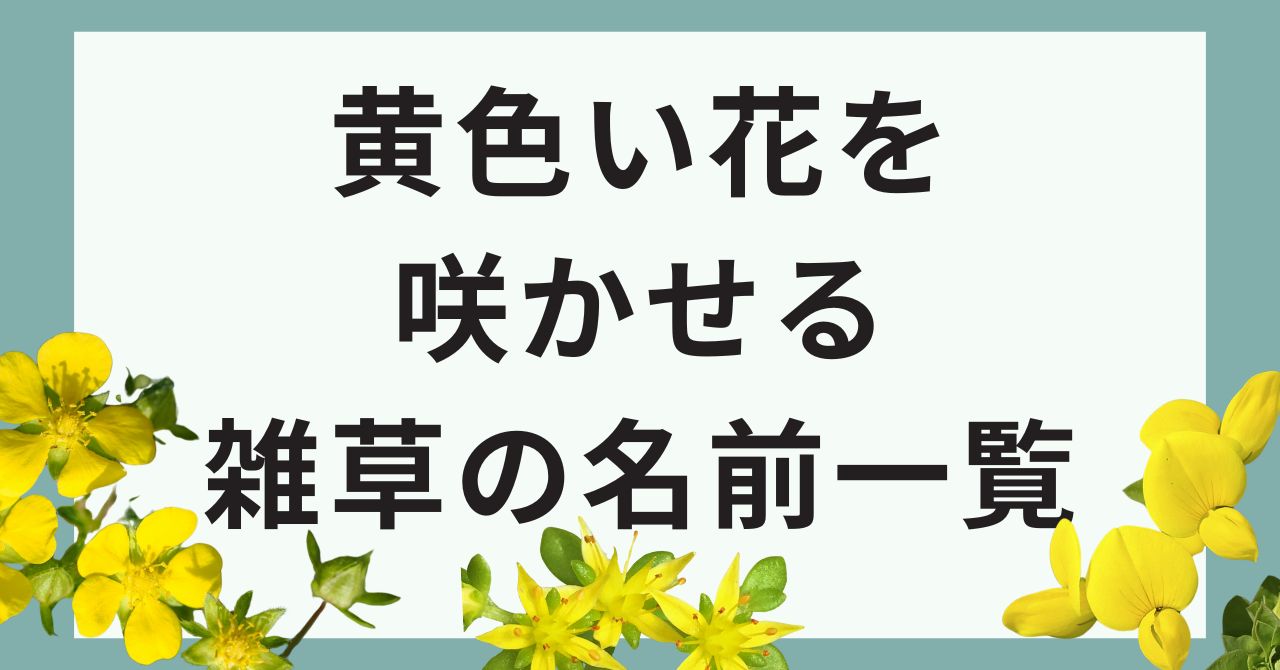
庭や道端にふと目を向けると、黄色い小さな花が可憐に咲いていることがあります。見た目は可愛らしくても、それらは多くの場合「雑草」として扱われる植物です。
中にはよく似た種類がいくつもあり、「黄色い花 雑草」と検索しても、なかなか名前が分からないという声も多く聞かれます。
この記事では、そんな黄色い花を咲かせる雑草の代表種を整理し、それぞれの特徴や見分け方をわかりやすくまとめました。庭の手入れや植物観察の参考として、ぜひ活用してみてください。
- 雑草の黄色い花の名前と特徴がわかる
- 種類ごとの見分け方がわかる
- それぞれの発生時期や分布がわかる
- 効果的な駆除方法がわかる
黄色い花の雑草の種類と見分け方
- 小さい黄色い花を咲かせる雑草
- たんぽぽに似た黄色い花の雑草
小さい黄色い花を咲かせる雑草
カタバミ(片喰)

- 花の特徴:小さな黄色い5枚の花弁を持つ花を咲かせ、直径1cm前後の可憐な見た目です。日差しのあるときだけ花を開き、曇りや雨の日は閉じてしまう性質があります。
- 原産地:日本を含む温帯地域
- 分布:日本全国に広く分布し、都市部や農地、庭先などでもよく見られます。
- 発生時期:春から秋にかけて花を咲かせますが、特に5月から9月が最も多く見られる時期です。
- 草丈:5cm~15cmほどと低く、地面を這うように成長します。
- 備考:繁殖力が非常に強く、地下茎や種子で広がります。駆除が難しいため、庭に生えると厄介とされることもあります。
カタバミの見分け方
- 葉がハート型で三つ葉状になっている
- 日中に花を開き、夕方には閉じる性質がある
- 根元近くに赤紫色の茎がある
- 茎が這うように地面を広がっている
オオキバナカタバミ(大黄花片喰)

- 花の特徴:カタバミよりも大きな黄色い花を咲かせ、直径2cm程度。中心がややオレンジがかって見えることがあります。
- 原産地:南アメリカ
- 分布:観賞用として持ち込まれた後、現在は日本各地で野生化しています。特に西日本で多く見られます。
- 発生時期:5月から10月ごろにかけて咲き続けます。温暖な地域ではより長期間花を咲かせることもあります。
- 草丈:10cm~25cm程度まで成長することがあります。
- 備考:見た目はカタバミに似ていますが、外来種であり、放置すると他の植物の成長を妨げることもあります。
オオキバナカタバミの見分け方
- カタバミより花が明らかに大きい
- 茎や葉が少し毛羽立っているように見える
- 日当たりのよい場所を好んで群生する
- 葉の緑色が明るく、やや光沢がある
コメツブツメクサ(米粒詰草)

- 花の特徴:米粒ほどの小さな黄色い花が密集して咲き、直径5mmほどと非常に小さいのが特徴です。
- 原産地:ヨーロッパ
- 分布:日本全国に分布し、道端や公園、空き地などで普通に見られます。
- 発生時期:4月から7月ごろにかけて開花します。
- 草丈:10cm〜30cmほどで、立ち上がるように成長します。
- 備考:マメ科の植物で、葉は三小葉のクローバー型です。踏まれても強く、踏圧に耐える性質があります。
コメツブツメクサの見分け方
- 花が非常に小さく、球状にまとまって咲く
- 葉はクローバーと同じく三枚葉
- 背丈が比較的高めに伸びる
- 花が密集して黄色い球のように見える
ミヤコグサ(都草)

- 花の特徴:鮮やかな黄色の蝶形花を数個まとめて咲かせます。花弁の形が独特で、マメ科特有の構造をしています。
- 原産地:日本および東アジア
- 分布:日本全国に見られ、特に草地や土手などの日当たりのよい場所に多く見られます。
- 発生時期:5月から8月にかけて開花します。
- 草丈:10cm〜30cm程度で、地面を這うように広がる場合もあります。
- 備考:マメ科の多年草で、花が終わると細長い実ができます。緑肥や緑化用にも利用されます。
ミヤコグサの見分け方
- マメ科特有の蝶形の花が特徴
- 茎は細く、地面を這うように伸びる
- 葉は小さめで5枚に見える形状
- 花が集まって房のようになることがある
コメツブウマゴヤシ(米粒馬肥)

- 花の特徴:ごく小さな黄色い花が球状に固まって咲き、直径は5mm以下です。
- 原産地:ヨーロッパ
- 分布:日本では都市部や道路脇、芝生などに多く見られます。
- 発生時期:5月〜8月にかけて開花します。
- 草丈:10cm〜20cmほどで、やや地面を這うように広がります。
- 備考:マメ科の一年草で、同じマメ科のコメツブツメクサと混同されやすいですが、こちらの方が花数がやや少なめです。
コメツブウマゴヤシの見分け方
- 花が極端に小さい
- 葉は細かく、やや艶がある
- 茎は地面に沿って伸びる
- 花後にできる実が巻貝のような形
オトギリソウ(弟切草)

- 花の特徴:鮮やかな黄色の花を5弁で咲かせ、中央部に黒点や線が入るのが特徴です。
- 原産地:日本、中国などの東アジア
- 分布:全国の野山や草地に分布。栽培種もあります。
- 発生時期:6月〜8月に開花します。
- 草丈:30cm〜60cmと高めで、雑草というより野草に近い存在です。
- 備考:古くから薬草としても知られ、民間療法で傷薬に用いられてきました。
オトギリソウの見分け方
- 花弁に黒い点状の模様がある
- 葉を透かすと黒い斑点が見える
- 草丈が高く、まっすぐに立つ
- 茎が赤みを帯びることがある
ハナニガナ(花苦菜)

- 花の特徴:淡い黄色の花を複数咲かせます。1つの花は直径2cmほどの舌状花です。
- 原産地:日本、中国、朝鮮半島など
- 分布:山野や草原、道端など幅広く分布します。
- 発生時期:5月から8月にかけて開花します。
- 草丈:20cm〜60cmと比較的高く育ちます。
- 備考:キク科の多年草で、食用になることもあります。名前の通り、葉に苦味があります。
ハナニガナの見分け方
- 葉が根元でロゼット状に広がる
- 花は細長い茎の先に咲く
- 花弁が薄く、明るい黄色
- 草丈がやや高く、茎が細長い
キジムシロ(雉蓆)

- 花の特徴:5枚の花弁を持つ小さな黄色い花で、直径1〜2cm程度。明るいレモンイエローが印象的です。
- 原産地:日本、中国、朝鮮半島などの東アジア
- 分布:本州・四国・九州の草地や道端に広く分布
- 発生時期:4月〜6月頃に花を咲かせます
- 草丈:10cm〜30cmほどで、地面を這うように広がります
- 備考:バラ科の多年草で、細いランナー(匍匐茎)を伸ばしながら増えます。名前は「雉(キジ)が座るほど広がる」姿から。
キジムシロの見分け方
- 三小葉が集まった特徴的な葉形
- 茎は地面を這って節から根を出す
- 花の中心に小さな黒点が見える
- 芝生や草地にマット状に広がる
コナスビ(小茄子)

- 花の特徴:星型の黄色い花をつけます。直径は1cmほどと小さく、やや黄緑がかった色合いも見られます。
- 原産地:日本、中国、朝鮮半島
- 分布:日本全国の平地や山地の道端、草地などに分布
- 発生時期:5月〜7月にかけて花を咲かせます
- 草丈:5cm〜20cmと低く、地表を這うように広がります
- 備考:サクラソウ科の多年草で、花後にできる実が小さなナスに似ているためこの名がつきました。
コナスビの見分け方
- 星型の花が下向きに咲く
- 葉の表面にやや光沢がある
- 茎の節から根を出して増える
- 花よりも実の姿が目立つこともある
ヒレタゴボウ(鰭田牛蒡)

- 花の特徴:直径2〜3cmの黄色い5弁花を咲かせます。明るく鮮やかな黄色で、花の中央にオレンジ色が差します。
- 原産地:北アメリカ
- 分布:湖沼や水辺に自生し、九州〜関東で特に増加傾向にあります
- 発生時期:6月〜9月の夏季
- 草丈:30cm〜60cm程度、水辺では茎を這わせながら成長
- 備考:特定外来生物に指定されており、河川や池に広がると生態系への影響が懸念されます。
ヒレタゴボウの見分け方
- 水辺に群生していることが多い
- 葉はやや丸みがあり厚い
- 繁殖力が非常に高く、水面を覆うように広がる
- 日本の在来種にはない鮮やかな色味
ケキツネノボタン(毛狐の牡丹)

- 花の特徴:直径1〜1.5cmの黄色い5弁花で、光沢のある花びらが特徴的です。中央の雌しべが球状に盛り上がって目立ちます。
- 原産地:日本(在来種)
- 分布:全国に広く分布し、湿った田んぼのあぜや水辺近くで見られます
- 発生時期:4月〜7月
- 草丈:30〜60cmほど
- 備考:トゲのある実ができ、触れると引っかかるような感触があります。全草に有毒成分を含みます。
ケキツネノボタンの見分け方
- 光沢のある黄色い5弁花
- 葉は3裂し、ギザギザが目立つ
- 茎や葉に毛が多い
- 湿った場所を好む傾向がある
コマツヨイグサ(小待宵草)

- 花の特徴:花径1〜2cmの明るい黄色の4弁花。夕方〜夜間に咲き始め、翌朝にはしぼみます。
- 原産地:北アメリカ
- 分布:日本全国に帰化し、道端や空き地、河川敷などでよく見かけます
- 発生時期:5月〜10月
- 草丈:10cm〜60cm程度
- 備考:マツヨイグサ属の帰化植物で、開花が夕方から始まるのが特徴。花は日中には閉じていることが多いです。
コマツヨイグサの見分け方
- 夜間や早朝に花が開いている
- 花びらが4枚で十字形
- 葉は細長く、互生で生える
- 茎に赤みが差す個体も多い
コモチマンネングサ(子持万年草)

- 花の特徴:星形の黄色い5弁花を咲かせ、花径は1cmほど。株全体が明るい緑から黄色に見えることもあります。
- 原産地:中国〜朝鮮半島
- 分布:日本全国に帰化し、庭、石垣、歩道脇などに多く自生
- 発生時期:5月〜7月
- 草丈:5cm〜15cmと非常に低く、地面を覆うように広がる
- 備考:ベンケイソウ科の多年草で、茎の先に子株(むかご)をつけて増えることが名前の由来です。
コモチマンネングサの見分け方
- 茎先に小さな子株をつける
- 多肉質の葉が密生している
- 乾燥に非常に強く、舗装の隙間にも生える
- 草丈が極めて低く、広がるように生える
スカシタゴボウ(透田牛蒡)

- 花の特徴:黄色い4弁花をつけ、花径は5mm程度と非常に小さいです。十字形に開いた花がいくつも枝分かれして咲きます。
- 原産地:ヨーロッパ
- 分布:日本全土に帰化。田畑や畦道、道端などに広く見られます
- 発生時期:4月〜6月
- 草丈:20cm〜60cm程度
- 備考:アブラナ科の一年草で、見た目は雑草のナズナなどにも似ています。名前は茎が中空で透けて見えることに由来します。
スカシタゴボウの見分け方
- 黄色い花が十字状で、非常に小さい
- 茎が中空で折ると透ける
- 葉は切れ込みがあり、茎を抱くようにつく
- 果実は細長く、縦に裂ける
スイカズラ(吸葛)

- 花の特徴:つぼみは白、咲き進むと黄色に変化する2色のラッパ形花が咲きます。花の長さは3〜4cmで甘い香りがあります。
- 原産地:日本、中国(在来種扱い)
- 分布:日本全土の山野や林縁、道端などに広く自生
- 発生時期:5月〜6月
- 草丈:つる性で、数m以上に伸びる
- 備考:スイカズラ科の常緑つる性植物。別名「金銀花」とも呼ばれ、薬用にも利用されます。花の蜜を吸って遊ぶことから名がつきました。
スイカズラの見分け方
- 白から黄色に色が変わる花
- 甘い香りが強く漂う
- つる性で木やフェンスなどに絡む
- 葉は対生し、楕円形で革質
たんぽぽに似た黄色い花の雑草
セイヨウタンポポ(西洋蒲公英)

- 花の特徴:濃い黄色の花が茎の先端に1輪咲きます。花弁は細かく多数あり、花全体は2cm〜4cmほどの大きさです。
- 原産地:ヨーロッパ
- 分布:日本全国に広がっており、特に都市部では在来種よりも多く見かけます。
- 発生時期:3月から5月が主な開花期ですが、地域によっては秋まで断続的に咲くこともあります。
- 草丈:10cm〜30cm程度ですが、花茎だけが直立して伸びるのが特徴です。
- 備考:在来のカントウタンポポやカンサイタンポポと混同されがちですが、外来種で繁殖力が強いです。
セイヨウタンポポの見分け方
- 花の根元に反り返る総苞片がある(在来種との大きな違い)
- 茎に毛が少なく、空洞になっている
- 根生葉がロゼット状に広がる
- 綿毛が大きく、種子が風に乗って遠くまで飛ぶ
ブタナ(豚菜)

- 花の特徴:タンポポに似た黄色い花を咲かせますが、茎が枝分かれして複数の花をつけるのが特徴です。
- 原産地:ヨーロッパ
- 分布:北海道から九州まで全国に分布。道端や芝地などによく見られます。
- 発生時期:5月から9月にかけて花を咲かせます。
- 草丈:20cm〜60cmと比較的高く成長します。
- 備考:見た目がタンポポに似ているため「タンポポモドキ」とも呼ばれます。多年草で繁殖力も強いです。
ブタナの見分け方
- 茎が枝分かれして複数の花を咲かせる
- 根生葉は細長く、切れ込みが少ない
- 茎に毛が少なく、真っ直ぐに立つ
- 花はタンポポよりもやや小ぶり
ジシバリ(地縛り)

- 花の特徴:直径1cmほどの小さな黄色い花を地面に沿って咲かせます。タンポポに似た舌状花ですが、より小型です。
- 原産地:日本・中国・朝鮮半島
- 分布:日本全国に分布し、特に芝生や庭先、空き地などでよく見かけます。
- 発生時期:4月から6月が開花時期です。
- 草丈:5cm〜10cm程度で、地面を這うように広がります。
- 備考:キク科の多年草で、地面を縛るように広がる姿から名前がついています。
ジシバリの見分け方
- 地面を這うように茎が伸びる
- 花は1茎に1つだけ付く
- 葉は丸みを帯びていて、互い違いに生える
- 根元から広がるように群生する
オオジシバリ(大地縛り)

- 花の特徴:直径2cmほどの黄色い舌状花を咲かせます。ジシバリより大きく、より明るい色合いが特徴です。
- 原産地:日本
- 分布:本州以南に分布し、道端やあぜ道などで見られます。
- 発生時期:4月から6月にかけて開花します。
- 草丈:10cm〜20cm程度。地面を這うように広がりながら伸びます。
- 備考:ジシバリと似ていますが、花が大きく、葉も厚みがあります。
オオジシバリの見分け方
- ジシバリよりも花が大きい
- 葉に光沢があり、厚めで丸い
- 花茎が少し立ち上がる
- 開花時に複数の花を同時に咲かせることが多い
コオニタビラコ(小鬼田平子)

- 花の特徴:非常に小さな黄色の舌状花が数輪まとまり、花径は約5〜8mmほど。タンポポに似ていますが花はより繊細です。
- 原産地:日本(在来種)
- 分布:全国の道端、草地、公園などによく生えます
- 発生時期:3月〜6月
- 草丈:10〜30cm程度
- 備考:「春の七草」のひとつである「ホトケノザ」はこの植物を指します(シソ科のホトケノザとは別種)。
コオニタビラコの見分け方
- 花はごく小さく、数輪がまとまって咲く
- 茎は地面近くから直立し数本立ち上がる
- 葉はへら形で、根元に集まるように付く
- 春先にいち早く開花し始める
黄色い花が咲く雑草の駆除方法
雑草の駆除方法
雑草を効果的に駆除するには、目的や環境に合った方法を選ぶことが大切です。黄色の花を咲かせる雑草も例外ではなく、放っておくと増えやすいため、定期的な管理が欠かせません。
手で抜き取る
特徴:
もっとも基本的で安心な方法です。小規模の庭や花壇などに向いています。
やり方:
・土が湿っているときに根元をしっかり持って抜く
・根が残ると再生するため、スコップや草抜き器を併用するのがおすすめ
注意点:
・根が深い雑草は途中で切れやすい
・種ができる前(花が咲いた直後など)に抜くと繁殖を抑えやすくなります
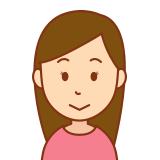
立ったまま草取りが出来て「ラクになった!」の口コミ多数!
除草剤の使用
特徴:
成分によって根まで枯らすことが可能。雑草の種類や目的に応じた製品選びが重要です。
やり方:
・非選択性(広範囲向け)と選択性(特定の雑草のみ)の違いを理解して選ぶ
・無風の日を選び、散布範囲に注意しながら使用する
注意点:
・野菜・花・ペット・子どもがいる場所では使用を控えるか慎重に扱う
・地面に残る成分がある場合は、他の植物への影響も考慮する必要があります
防草シート・マルチング
特徴:
雑草を「生やさない」ための予防策。特に種の発芽を抑えるのに効果的です。
やり方:
・土の上に防草シートやバークチップを敷く
・隙間がないように敷き詰めるのがポイント
注意点:
・既に生えている雑草はあらかじめ除去しておく
・数年で劣化することがあるため、定期的な張り替えが必要
雑草は種類や生育状況によって対処法が異なります。単独の方法だけでなく、複数の手段を組み合わせることで、より効果的に雑草の管理が可能です。雑草は見た目に紛れやすく、放置すると急速に広がることもあるため、日頃からの小まめな対応が鍵となります。
黄色い花を咲かせる雑草の種類と特徴まとめ
- 黄色い花を咲かせる雑草は春から秋にかけて広く見られる
- 原産地は日本在来種と外来種が混在している
- 小さな黄色い花でも繁殖力が非常に高い種が多い
- カタバミ類は日照に応じて花の開閉を行う特徴がある
- マメ科の雑草は三枚葉や蝶形花などで識別が可能
- タンポポに似た外来種は花茎の構造で見分けやすい
- 多くは道端や空き地、芝生などの身近な場所に分布
- 花の大きさや形状が種類ごとに大きく異なる
- 湿地を好む種や乾燥地に強い種など環境適応が多様
- 光沢のある花びらや独特の実の形が見分けの手がかり
- 葉の形や生え方で判別できる種も多い
- 地面を這うように広がる低草丈のものが多い
- 駆除が難しいほどの繁殖力を持つものも存在する
- 中には有毒成分を含む雑草もあるため注意が必要
- 花の色味や咲く時間帯も識別の重要なポイント