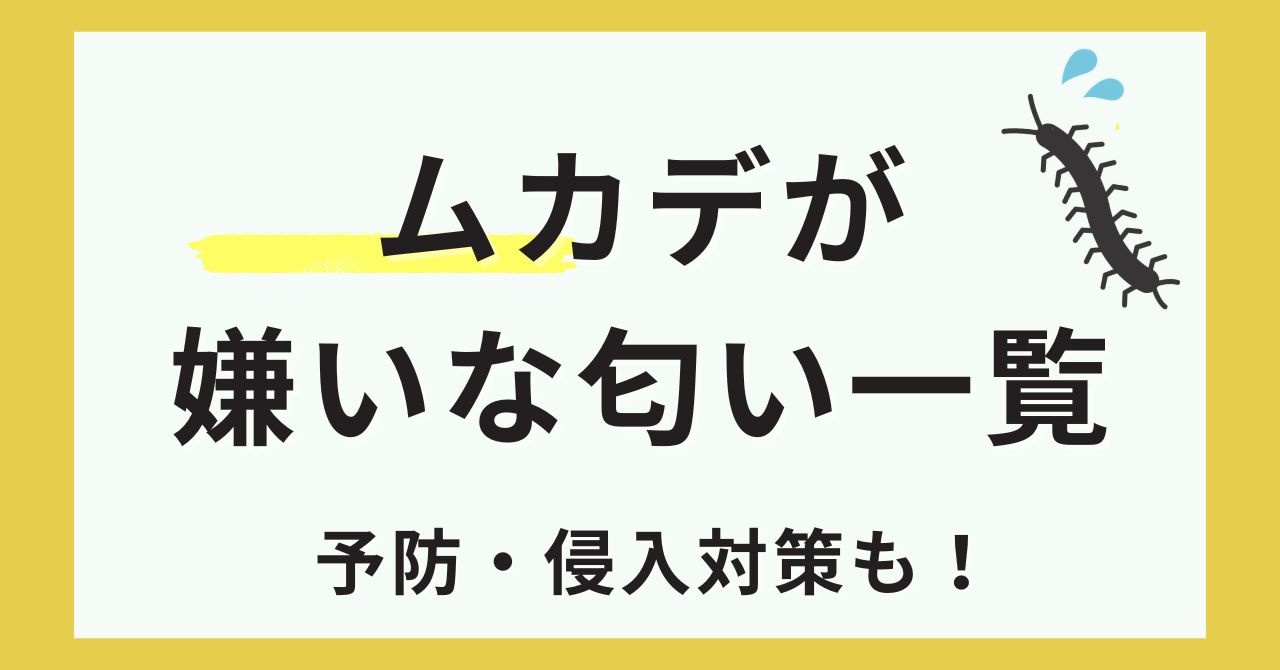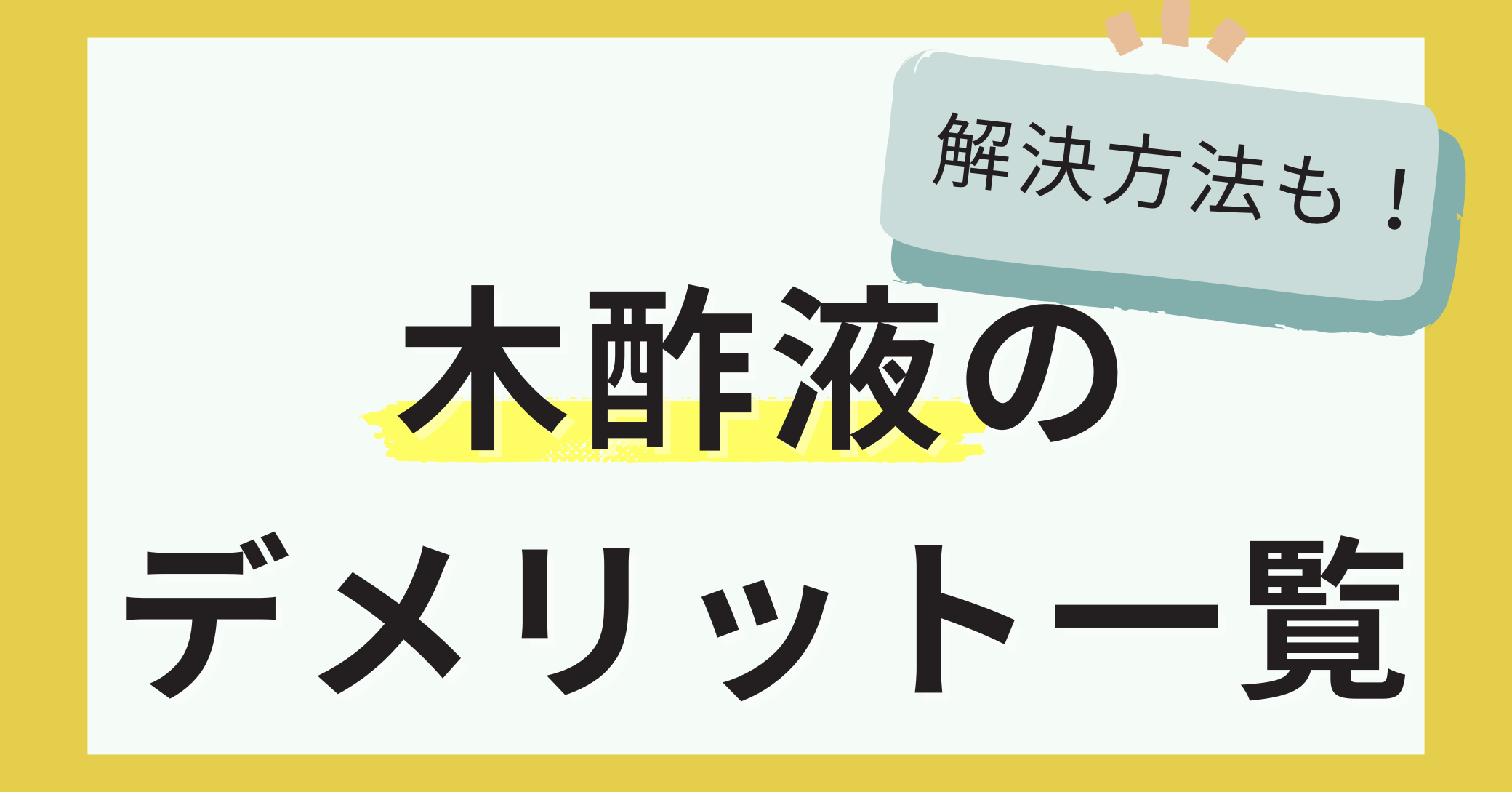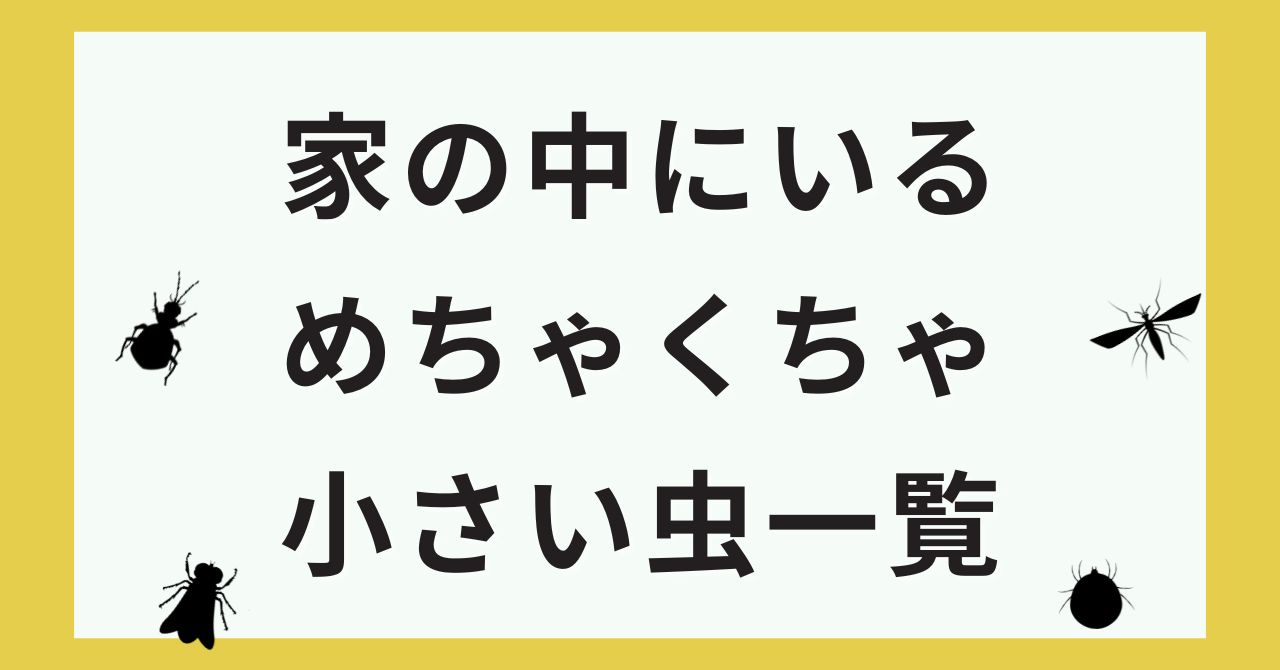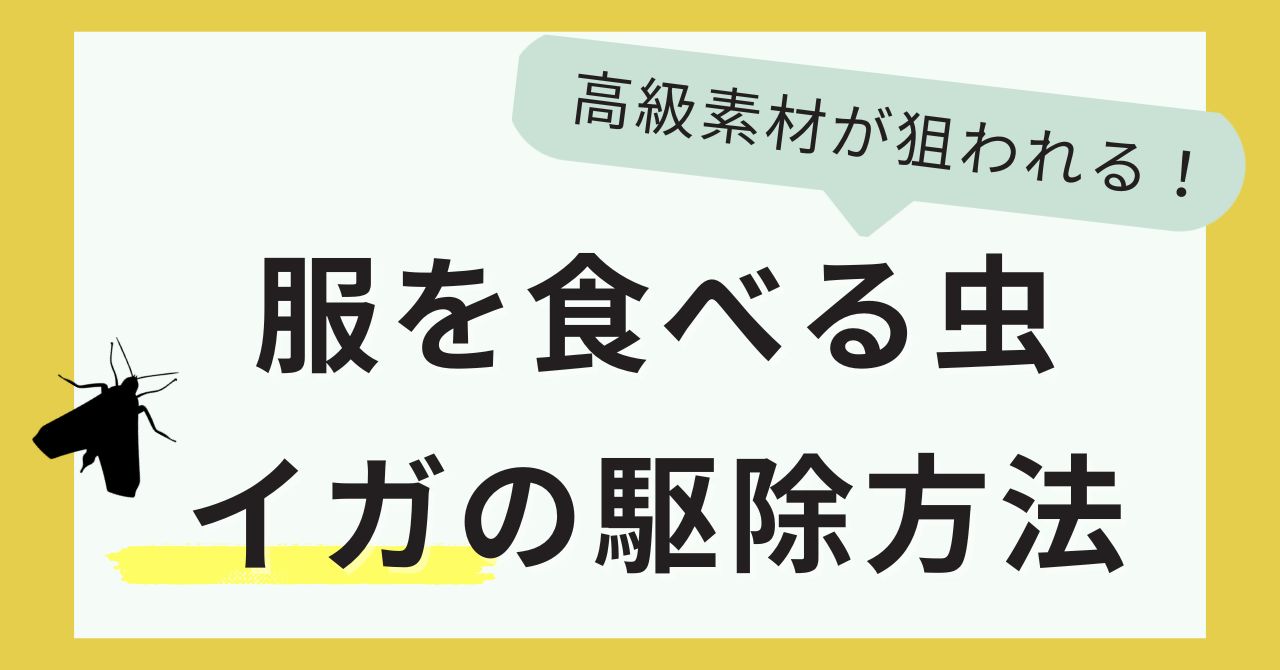ムカデの毒はどこにある?危険性と刺されず駆除するための予防法
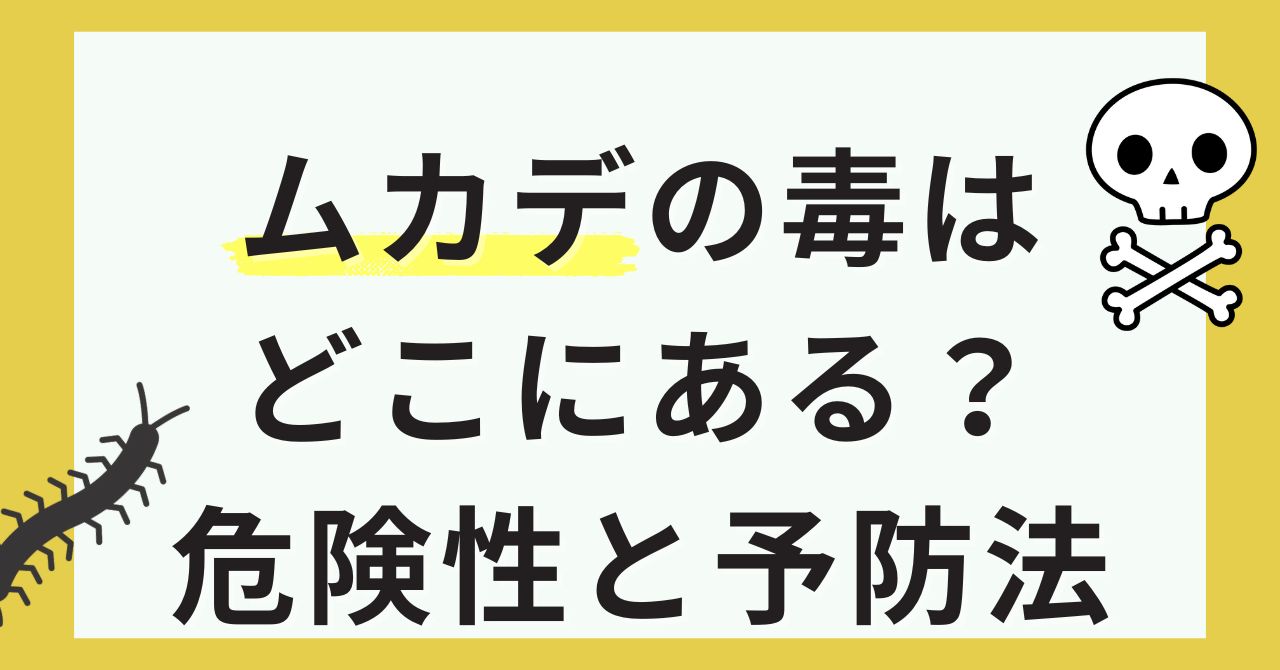
ムカデに関する疑問の中でも、「ムカデの毒はどこにある?」といった検索は、実際に見かけたり被害を受けたりした方にとって非常に切実なテーマです。
本記事では、ムカデの毒がどこから出るのかを中心に、ムカデの毒成分やその影響、またムカデの足は何本あるのか、何類に分類されるのかといった基本情報まで網羅的に解説していきます。
さらに、ムカデは何を食べるのか、どこにいるのか、どの時期や活動時期に注意が必要なのか、ムカデを食べる生き物との関係にも触れています。ムカデの繁殖期や卵の特徴、ムカデの種類を写真付きで紹介することで、種類の見分けにも役立てていただけます。
これからの季節、特にムカデが活発になる時期には、正しい知識を持って対応することが安全な生活環境づくりにつながります。ムカデへの不安を減らし、適切な対策をとるための参考にしてください。
- ムカデの毒はどこから出るかがわかる
- ムカデの毒成分とその作用が理解できる
- 毒を持つムカデと持たない虫の違いがわかる
- 毒を防ぐための駆除と予防の方法が学べる
ムカデの毒はどこにある?どんな毒?
- ムカデの毒はどこから出る?
- ムカデの毒の成分とは
- ムカデの毒は人によって症状が違う?
- ムカデに刺されないための駆除方法
- 毒を持たないムカデの種類はいるのか?
ムカデの毒はどこから出る?
ムカデの毒は、あごの先端にある「毒腺」から分泌されます。具体的には、ムカデの頭部にある大あご(顎肢=がくし)の中に毒腺があり、そこから毒を注入する構造になっています。
この下にはムカデのアップ写真がありますのでご注意ください。

この大あごは、見た目には脚のように見えるため気づきにくいのですが、ムカデにとっては獲物を捕らえるための主要な武器です。毒腺はこの大あごの内側にあり、噛みつく際に毒液が流れ出て相手に注入される仕組みになっています。
ムカデの毒は神経毒やタンパク質分解酵素などが含まれており、これにより噛まれた箇所が赤く腫れたり、激しい痛みを引き起こすことがあります。体の大きい個体ほど毒の量も多くなるため、咬傷の症状も重くなる傾向があります。
このため、ムカデを見つけた場合は素手で触れず、専用の道具や厚手の手袋を使って対処することが大切です。また、夜間に活発に動き回ることが多いため、特に寝具や靴の中など、直接肌に触れる場所には注意が必要です。
毒が出る部位を理解しておくことで、遭遇時の対応や予防策にもつながります。
ムカデの毒の成分とは
ムカデの毒には、複数の成分が含まれており、それぞれが異なる作用を持っています。主な成分には、ヒスタミン、セロトニン、ヒアルロニダーゼなどが挙げられます。
これらの成分は、人体に対してさまざまな影響を与える性質があります。たとえばヒスタミンは、アレルギー反応や炎症の原因となる物質で、噛まれた部分に腫れやかゆみ、赤みなどを引き起こします。セロトニンには神経を刺激する作用があり、痛みや筋肉の収縮を誘発することがあります。
また、ヒアルロニダーゼといった酵素は、組織の細胞間の結合を緩め、毒の成分が体内に浸透しやすくする働きを持っています。このため、ムカデに噛まれた際の症状は、単なる刺傷にとどまらず、じんわりと広がる痛みや熱感をともなうことがあります。
体質や噛まれた場所によっては、これらの毒成分に対する反応が強く出ることもあり、特に小さな子どもや高齢者、アレルギー体質の人は注意が必要です。腫れがひどい、熱が出る、呼吸が苦しいといった症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診するようにしましょう。
このように、ムカデの毒は複数の刺激物質と酵素の混合物で構成されており、その組み合わせによって痛みや炎症が引き起こされるのです。適切な対処を知っておくことで、被害を最小限に抑えることができます。
ムカデの毒は人によって症状が違う?

ムカデに噛まれたときの症状は、人によって大きく異なることがあります。これは体質や年齢、噛まれた場所、さらにはムカデの種類や毒の量によって反応が変わるためです。
まず、ムカデの毒には複数の成分が含まれており、それぞれが痛み・腫れ・かゆみ・熱感などの症状を引き起こします。一般的には噛まれた直後にズキズキとした痛みがあり、数時間以内に赤みや腫れが広がることが多いです。しかし、まったく痛みを感じない人もいれば、逆に激しい炎症やアレルギー反応を起こす人もいます。
特に、アレルギー体質の方や過去にムカデに噛まれた経験がある人は、強い免疫反応が出ることがあります。呼吸が苦しくなったり、じんましんや発熱などの全身症状が出る場合は、すぐに医療機関での処置が必要です。
一方で、子どもや高齢者は皮膚が薄く、毒の影響を受けやすいため、軽い症状でも念のため注意が必要です。痛みがなくても腫れがひどい、発熱が続くなどの場合には、病院で診てもらうのが安心です。
このように、ムカデの毒に対する反応は個人差が大きいため、過信せず、噛まれたあとは必ず患部の観察と適切なケアを行いましょう。判断に迷うときは、専門医の意見を仰ぐことが大切です。
ムカデに刺されないための駆除方法
ムカデに刺されないためには、単に目の前の個体を退治するだけでなく、侵入を防ぎ、住みにくい環境を整えることが重要です。
- 侵入経路を塞ぐ
玄関、窓のすき間、通気口などにパテや隙間テープを使って外部とのすき間を遮断する - 湿気を減らす
除湿機や換気で浴室・押し入れ・床下などの湿気を抑え、ムカデが好む環境をなくす - 香りによる忌避対策
ハッカ油やヒノキ系のスプレーでムカデの侵入しやすい場所に匂いのバリアを作る - 室内外を整理整頓する
段ボール、新聞紙、落ち葉、石などのムカデの隠れ場所を取り除く - ペットや子どもに配慮した対策を選ぶ
天然由来の忌避剤など、安全性の高いアイテムを選ぶようにする
- 日中に潜みやすい場所をチェック
布団の下、家具の裏、押し入れの奥など暗くて湿った場所を定期的に確認する - 夜間の活動に注意する
ムカデは夜行性のため、就寝前に寝室や浴室をチェックしておくと安心 - 見失ったときはバリアを作る
香りのスプレーや蚊帳、防虫ネットなどで、寝具周辺をガードする
- 即効性のある殺虫スプレーを使う
ムカデ専用またはピレスロイド系のスプレーで頭部や脚の付け根を狙う - 薬剤が苦手な場合は凍結スプレーを使用する
-80℃前後の冷却スプレーでムカデを凍らせて動きを止める - 死骸はすぐに処理する
放置せず、密閉できる袋に入れて廃棄し、他の虫を呼び寄せないようにする - 再発を防ぐために害虫駆除も並行して行う
ムカデのエサとなるゴキブリやクモをあらかじめ駆除しておく
このように「予防・発見・駆除」の3ステップで対策することで、ムカデに刺されるリスクを減らし、安心して生活することができます。
毒を持たないムカデの種類はいるのか?
ムカデの仲間には多くの種類が存在しますが、基本的に「ムカデ」と呼ばれるものの大半は毒を持っています。ただし、広い意味で「ムカデのように見える虫」の中には、毒を持たない種類も存在します。
まず、生物学的に「ムカデ類(オオムカデ目)」に分類されるものは、ほぼすべてが毒を持つ捕食性の生き物です。これらは前脚が毒腺とつながっており、小動物や昆虫を捕らえて麻痺させるために毒を利用します。したがって、一般的なムカデには「毒がない種」はいないと考えて差し支えありません。
しかし、見た目が似ている「ヤスデ」や「ゲジゲジ」などは誤解されやすい存在です。


たとえば、ヤスデはムカデと同じようにたくさんの足を持ちますが、攻撃性はなく毒腺もありません。刺激を受けると臭い液体を出すことはありますが、人を噛んだり刺したりすることはありません。
また、ゲジゲジも毒はありますが、人に対して積極的に危害を加えることはまれで、多くの場合は益虫として扱われています。
このように、「毒を持たないムカデ」というよりも、「ムカデに似ているが毒を持たない虫」がいるというのが正確な表現です。見た目で判断せず、種類を正しく見極めることが大切です。安全かどうかの判断に迷ったときは、専門家の意見を参考にしましょう。
どこに気を付ける?ムカデの毒と生態
- ムカデの足は何本あるのか
- ムカデは何類に分類される?
- ムカデの種類を写真で紹介
- ムカデの活動時期と出現の傾向
- ムカデはどこにいる?生息環境の特徴
- ムカデの繁殖期はいつ?卵の特徴は?
- ムカデは何を食べるのか?
- ムカデを食べる生き物とは?
ムカデの足は何本あるのか

ムカデの足の本数は種類によって異なりますが、基本的には「奇数の節」に対して1対ずつ足が生えている構造をしています。そのため、足の総数も奇数の倍、つまり常に偶数本になります。
一般的に見られるムカデの足の数は30本から最大で354本程度とされ、体の節の数に比例して足の本数も増減します。特に大型の種類では節の数が多いため、それに伴って足の本数も増える傾向があります。
例えば、日本でよく見られる「トビズムカデ」では、足の本数は60本前後になります。体の両側に均等に並んでいて、左右に1本ずつ対になって生えているため、左右対称の姿をしています。
ここで注意したいのは、「ムカデ」と呼ばれる虫のすべてが同じ足の数を持つわけではないという点です。幼虫の場合は成長とともに節が増えるため、脱皮を繰り返すことで徐々に足の本数も増えていきます。
このように、ムカデの足の数は「種類」「成長段階」によって違いがありますが、常に偶数本で、非常に多くの足を持つのが共通点です。見かけた際に足の本数を正確に数えるのは難しいかもしれませんが、観察の一つの指標になります。
ムカデは何類に分類される?
ムカデは「多足類(たそくるい)」に分類され、さらにその中の「唇脚類(しんきゃくるい)」というグループに属しています。これは節足動物門の中の一種で、昆虫やクモ、エビ・カニなどと同じ大きな分類に含まれています。
このように言うと昆虫の仲間のように思われがちですが、ムカデは昆虫類とは異なり、体が多数の節に分かれ、それぞれの節に1対の足を持つという点で特徴的です。昆虫は通常、3対6本の足を持ち、体が頭・胸・腹の3つに分かれていますが、ムカデはそうした区分がなく、細長い体に足がずらりと並ぶ構造をしています。


また、唇脚類にはムカデの他に「ヤスデ」や「ゲジゲジ」なども含まれますが、これらは分類上でさらに細かく分かれています。ムカデは肉食性で攻撃的な性質を持つ一方、ヤスデは腐葉土などを食べるおとなしい性格であるため、生態も異なります。

つまり、ムカデは節足動物門の中でも独自の特徴を持つ「唇脚類」に属し、昆虫とは異なる多足の捕食者として分類されています。構造や生態の違いを知ることで、ムカデの正確な位置づけが理解しやすくなります。
ムカデの種類を写真で紹介
ムカデには世界中でおよそ3000種以上が知られていますが、日本国内でも数十種が確認されています。その中でも特に身近で、家の周囲や屋内で見かける可能性が高い代表的な種類を、特徴とあわせて紹介します。
トビズムカデ(オオムカデ)

- 【体長】7〜12cm程度だが、20cm以上になる個体も存在
- 【色】黄褐色に黒い縞模様、頭が赤褐色
- 【特徴】胴体が短めで足が太い、比較的素早く動く
- 【出現場所】湿った場所、時に家屋の壁や風呂場付近
アオズムカデほどの危険性はないものの、咬まれると痛みを伴うことがあります。
アオズムカデ

- 【体長】10~20cmほど
- 【色】全体的に暗緑色や黒緑色、アカズムカデと異なり頭と胴体の色が同系色
- 【特徴】大型で攻撃性が高く、咬まれると強い痛みがある
- 【出現場所】屋外、特に落ち葉や石の下、時に屋内にも侵入
アオズムカデはトビズムカデの亜種。日本でもっとも有名で、人への被害も多い種類です。毒性が強いため注意が必要です。
セスジアカムカデ

- 【体長】6~10cmほど
- 【色】背中に赤褐色の線が通っている
- 【特徴】比較的小型で、民家周辺で見かけることも
- 【出現場所】庭の落ち葉の下や湿気の多い場所
比較的おとなしい性質ですが、触れると反射的に咬むこともあるため、油断は禁物です。
このように、ムカデの種類によって体長・色・性質が異なります。咬傷被害を防ぐためにも、見かけたムカデの種類を判断できるようにしておくと安心です。
ムカデの活動時期と出現の傾向

ムカデは一年中見かけるわけではなく、特に活発になる時期がはっきりしています。時期や環境を知っておくことで、予防や対策が立てやすくなります。
春(3月〜5月)
- 冬眠から目覚め、徐々に活動を再開する
- 気温と湿度の上昇に伴い、4月下旬〜5月にかけて活動が活発化
- 家の中にも侵入しやすくなるため、早めの対策が効果的
夏(6月〜8月)
- 6月は活動のピークで、産卵やエサ探しが盛んになる
- 真夏(7月〜8月)は暑さを避け、夜間に出現することが多い
- 涼しく湿った場所(浴室・床下・押し入れなど)に潜む
秋(9月〜11月)
- 9月頃に活動が再び活発化(第二のピーク)
- 冬眠に備えてエサを求めて動き回る
- 気温が下がり始めると徐々に活動が落ち着く
冬(12月〜2月)
- 気温の低下により、ほとんどのムカデは冬眠に入る
- 地中・落ち葉の下・家の床下などに潜んで過ごす
- 基本的には目にする機会がほとんどない
また、ムカデは雨の日や雨の直後にもよく現れます。これは、乾燥を嫌うムカデが湿度の高い場所を求めて移動するからです。梅雨時期や台風のあとなどは、室内に侵入してくる可能性が高まります。
このように、ムカデの活動時期は「春と秋の涼しく湿った時期」にピークを迎えます。出現の傾向を把握しておくと、スプレーの準備や忌避剤の設置時期なども的確に調整できるようになります。適切なタイミングで対策を行うことが、ムカデの侵入を未然に防ぐうえで重要です。
ムカデはどこにいる?生息環境の特徴

ムカデは湿気があり、暗くて静かな場所を好む生き物です。そのため、自然界では落ち葉の下、石の裏、朽ち木の中などに身を潜めています。これらの場所は乾燥を避けながら、身を守れる環境が整っているため、ムカデにとっては理想的な生息地といえるでしょう。
住宅の周辺では、庭の植木鉢の下やブロックのすき間、雑草の茂った場所に潜んでいることが多く、ここから室内へと侵入することがあります。特に雨が続いた後など、湿度が高いタイミングでは活発に行動するため、注意が必要です。
屋内に入り込むと、押し入れや洗面所の隅、床下の配管まわり、キッチンのすき間など、湿気と暗がりがそろった場所に留まる傾向があります。これらはムカデにとって身を隠しやすく、エサとなる虫が出やすいという点も影響しています。
このように、ムカデは常に「静か・暗い・湿った」環境を求めて移動しているため、住宅まわりでもこうした条件がそろう場所を重点的に点検し、対策をとることが重要です。
ムカデの繁殖期はいつ?卵の特徴は?
ムカデの繁殖期は、一般的に気温と湿度が上昇する初夏から秋にかけて活発になります。特に5月から6月、そして9月から10月にかけてがピークとされ、この時期に屋内でムカデを目撃する頻度も高まる傾向があります。
この時期になると、ムカデは静かで湿気の多い場所に産卵します。たとえば、落ち葉の下、倒木の隙間、石の裏、あるいは家の中であれば床下や押し入れなどが産卵場所となりやすいです。
卵の特徴としては、直径1〜2mmほどの白っぽい粒状で、数十個をひとまとまりにして産むことが多いです。親ムカデは卵に覆いかぶさるようにして保護する習性があり、この期間は外敵から卵を守るために攻撃的になることもあります。
また、孵化後すぐに脚を持った幼虫が現れ、何度も脱皮を繰り返しながら成長していきます。卵や幼虫は目立ちにくく、発見が遅れがちになるため、梅雨時期や秋の長雨シーズンには特に注意が必要です。
このように、ムカデの繁殖期と卵の存在は、見た目以上に身近な脅威になる可能性があります。湿度管理と物陰の清掃をこまめに行うことで、繁殖環境をつくらない工夫が大切です。
ムカデは何を食べるのか?

ムカデは主に肉食性で、小さな昆虫や節足動物を捕食する習性があります。そのため、ゴキブリやクモ、ダンゴムシ、ワラジムシ、シロアリなどがムカデのエサとしてよく知られています。
このような捕食対象は、いずれも湿った暗所に生息していることが多く、ムカデが家の中や庭の隅などに現れるのは、そうした獲物を探しているためです。また、ムカデは非常に俊敏で、鋭いアゴを使って獲物に毒を注入し、動きを封じてから捕食します。
さらに、種類によっては同種や他の小動物を襲うケースもあります。これはムカデが基本的に単独で生活し、縄張り意識が強いことにも関係しています。
一方で、ムカデは植物や食品を好むことはなく、人間が食べるようなものを荒らすことはほとんどありません。つまり、食べ物の衛生面での被害よりも、他の虫を追ってやってくる“二次被害”としてのリスクが大きいのです。
このように考えると、ムカデ対策はエサとなる害虫を減らすことが基本になります。室内の清掃や湿気対策に加えて、ゴキブリなどを見かける頻度が多い家庭では、ムカデも出やすくなると意識しておくと良いでしょう。
ムカデを食べる生き物とは?

ムカデは毒を持つことで知られていますが、それでも捕食する生き物は存在します。自然界では、ムカデも食物連鎖の一部として狙われる側になることがあります。
主にムカデを食べるのは、ヘビや大型のカエル、トカゲなどの爬虫類・両生類です。これらの生き物はムカデの動きに素早く反応し、外骨格の隙間を狙って飲み込んでしまうことができます。特にヤマカガシなど一部のヘビは、ムカデの毒に対してある程度の耐性を持っているとされており、積極的に捕食することも確認されています。
また、野鳥の中でもムカデを捕食する種類がいます。例えば、ムクドリやカラスは雑食性であり、地面で動く虫を好んでついばむ傾向があります。ムカデのような動きのある虫もターゲットになり得るのです。
さらに、ムカデ同士が共食いをすることもあります。とくにエサが不足している環境では、同種を襲うケースが見られます。これは肉食性で単独行動をとるムカデならではの習性です。
このように、ムカデの天敵は意外と多く、自然の中ではさまざまな生物にとって貴重なタンパク源のひとつとなっています。したがって、ムカデの数が増えすぎないのは、こうした捕食者の存在による自然のバランスのおかげともいえるでしょう。
ムカデの毒がどこにあるかを知って安全対策
- ムカデの毒は大あごの中にある毒腺から分泌される
- ムカデの毒は咬まれると神経や皮膚に強く作用する
- 毒の主成分にはヒスタミンやセロトニンなどが含まれる
- 酵素によって毒が体内に浸透しやすくなる特徴がある
- ムカデの毒への反応は個人差があり体質で異なる
- アレルギー体質の人は強い反応が出る可能性がある
- 小児や高齢者は軽い咬傷でも注意が必要である
- ムカデ類は基本的に毒を持つ種が多い
- ムカデに似たヤスデやゲジゲジは毒を持たない
- ムカデの足の本数は種類によって異なり常に偶数である
- ムカデは多足類の唇脚類に分類される節足動物である
- 日本で見られるムカデにはトビズムカデなどがある
- ムカデの活動は春と秋に活発化する傾向がある
- 湿気が多く暗い場所にムカデは生息する傾向がある
- 繁殖期には卵を守る行動をとり攻撃的になることがある
- ムカデは肉食性でゴキブリなどの小動物を捕食する
- ヘビやカエルなどムカデを捕食する天敵も存在する