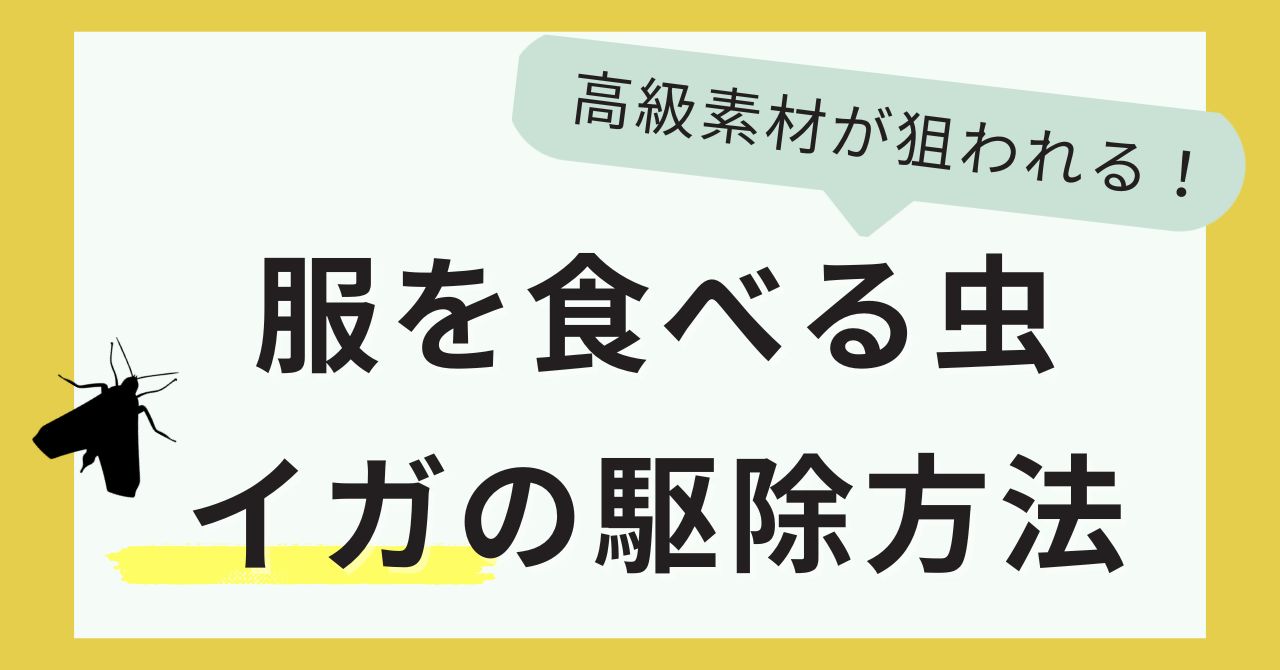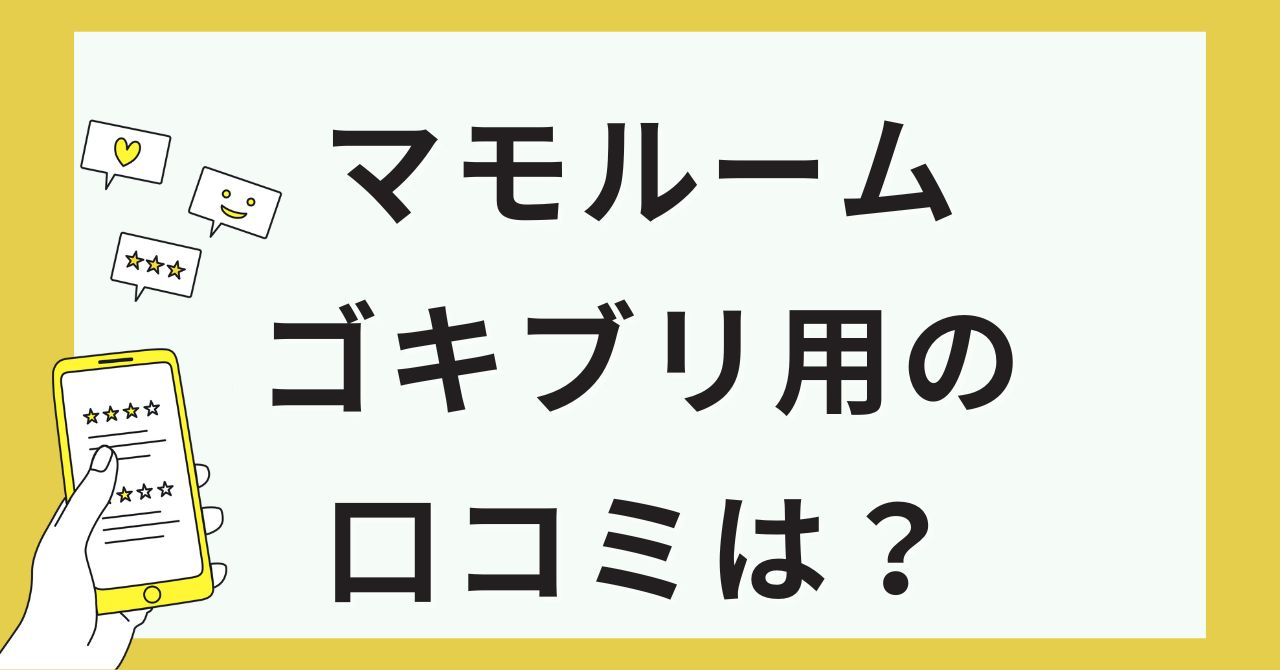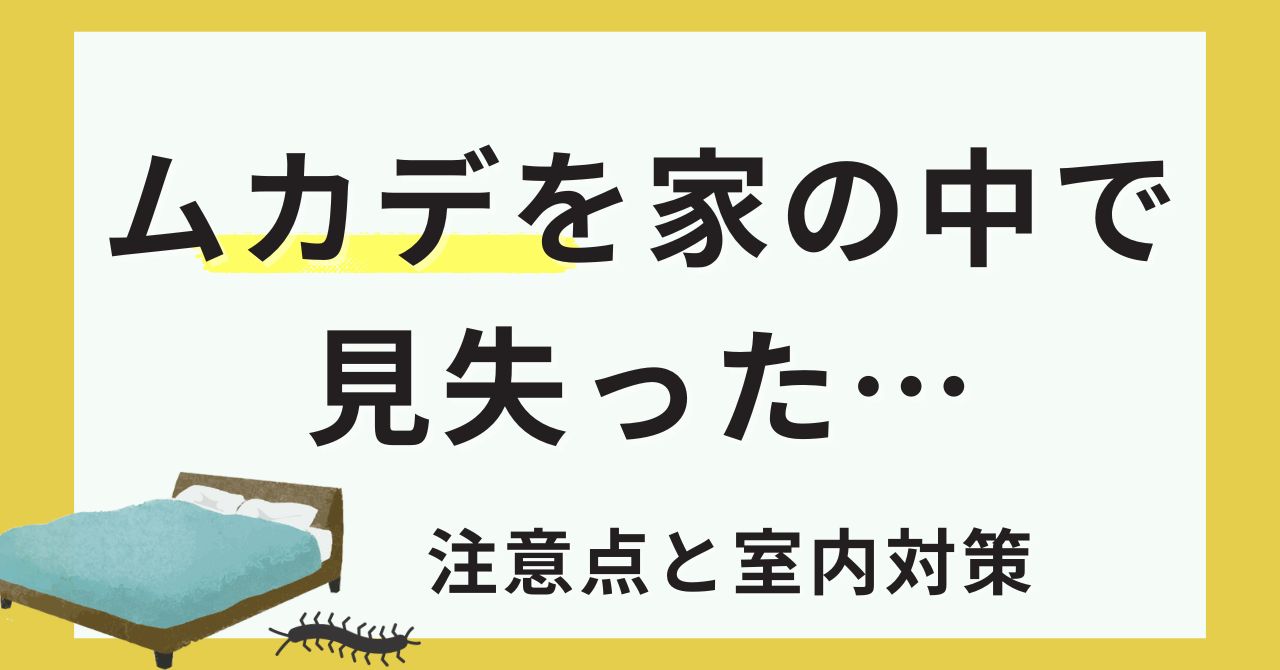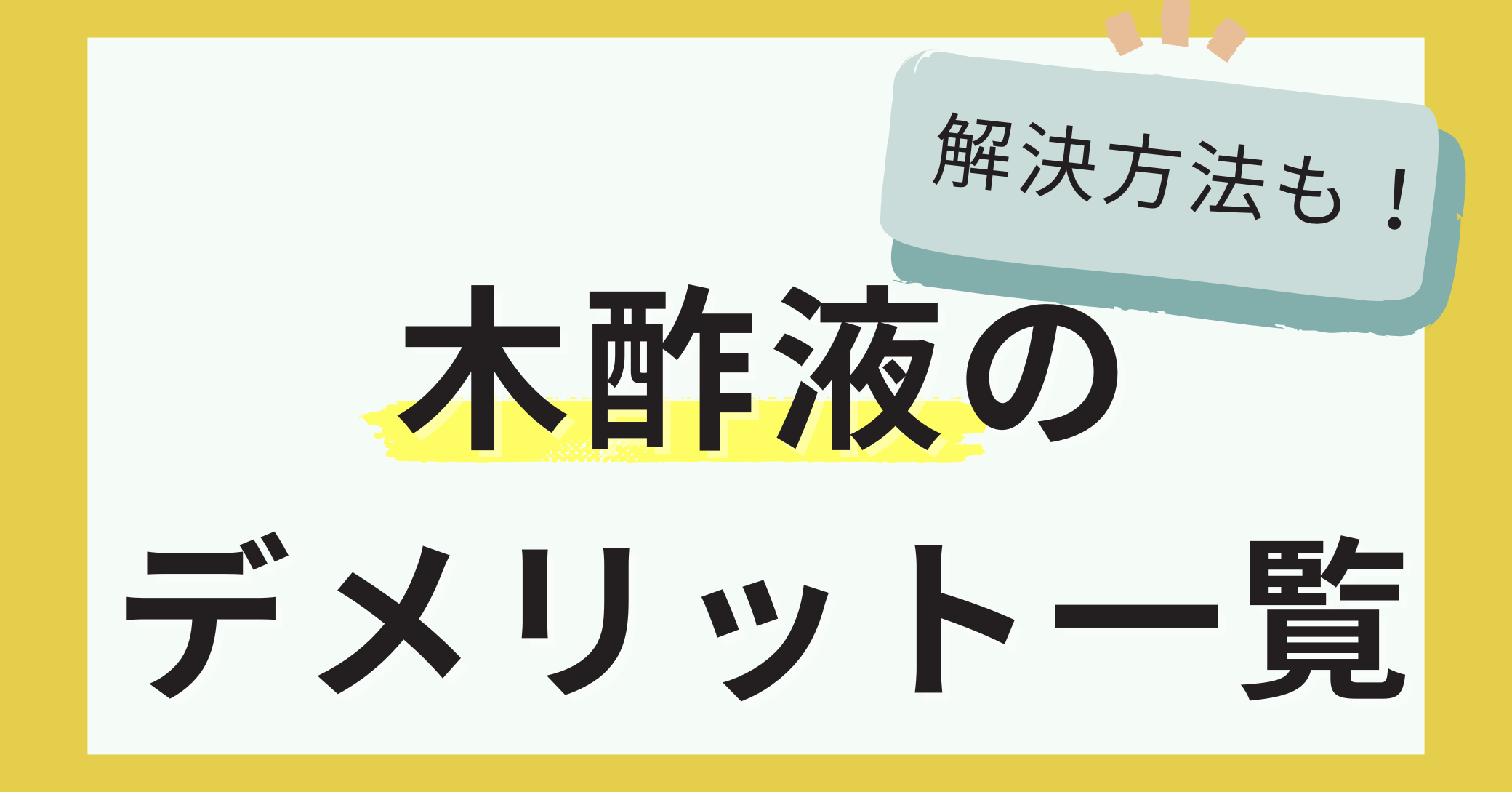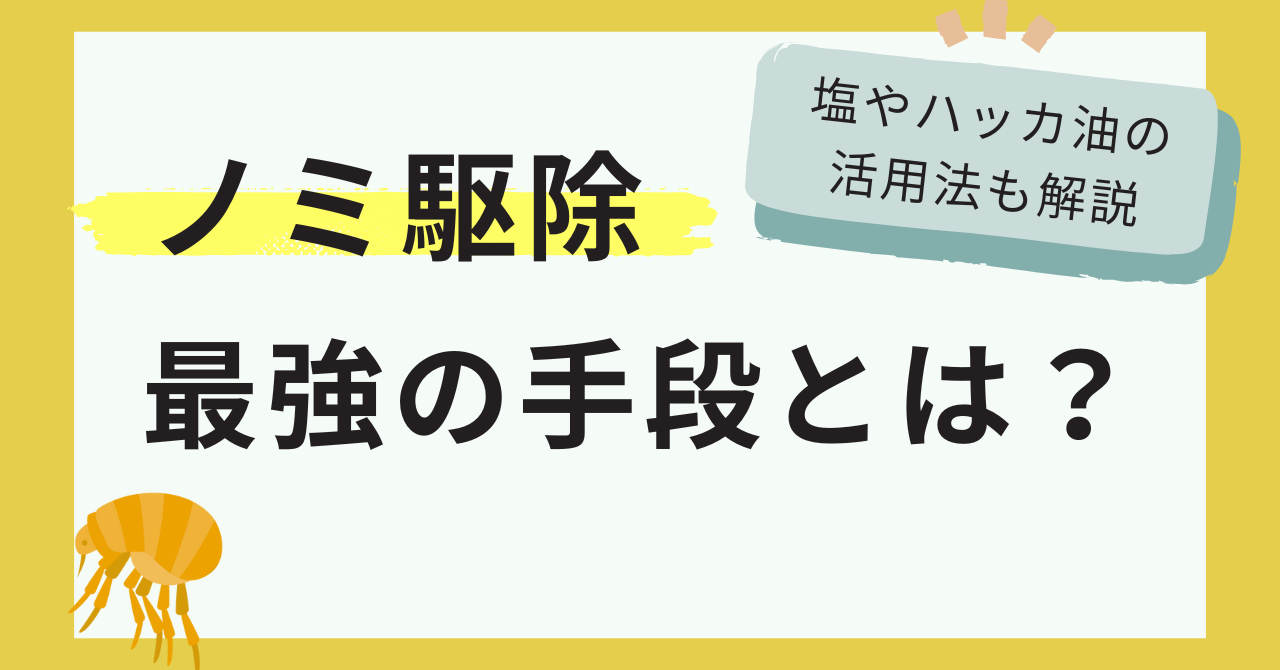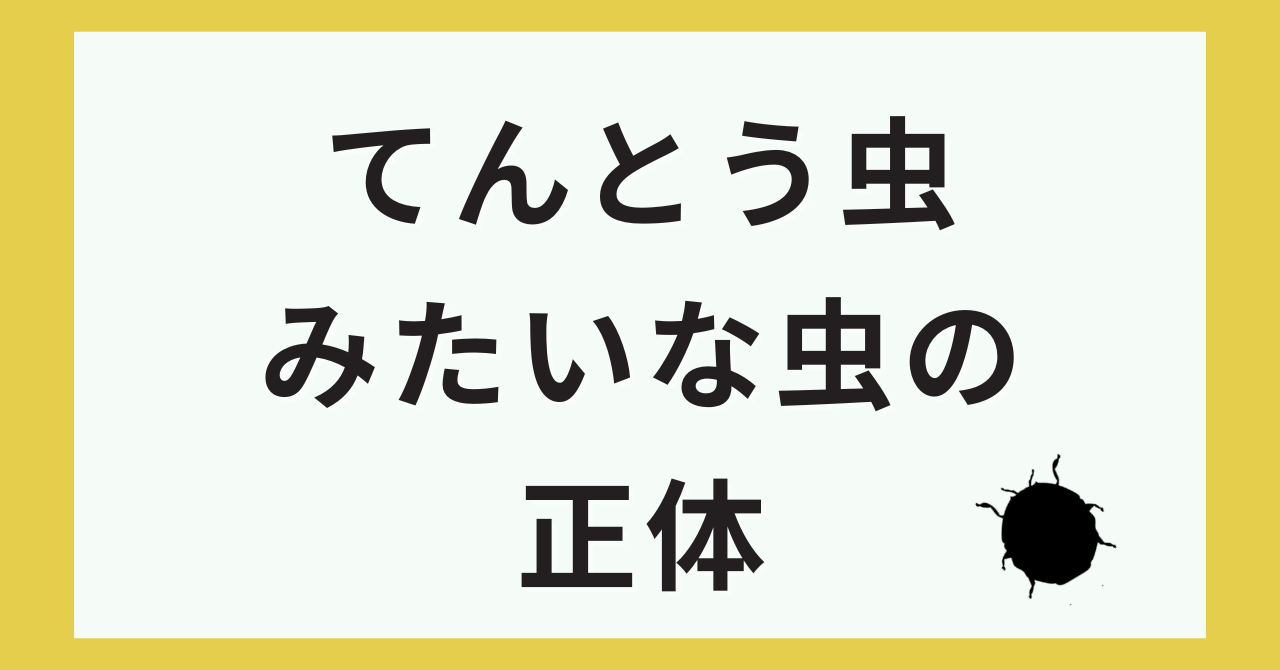スズメバチの種類&巣の形状で見分ける方法

庭先や軒下で蜂の巣を見つけ、スズメバチなのか、はたまた他の危険な種類なのか見分け方が分からず巣の扱いに不安を抱く人は少なくありません。
とくに巣の初期段階は小さく、気づきにくい一方で、季節が進むと急速に拡大するとされています。安全を優先しながら、観察ポイントを押さえ、危険を避けて対応を進めることが求められます。
代表的なオオスズメバチの巣やキイロスズメバチの巣の特徴を知っておけば、不要な接触を減らすことが出来ます。
本記事では、各自治体の案内や専門家の一般的な知見で整理されている内容を基に、行動手順と注意点をまとめます。
- 代表的なスズメバチの巣の見分け方と注意点
- 巣の初期段階
- 判別ポイントを写真でチェック
- 発見後の相談先や対処の流れ
スズメバチの種類と巣の見分け方①
- スズメバチの種類
- キイロスズメバチの巣の特徴
- オオスズメバチの巣の特徴
- その他のスズメバチの巣
- 巣の見分け方のポイント
スズメバチの種類
スズメバチにはさまざまな種類が存在し、それぞれ外見や性格、営巣場所などに特徴があります。日本に分布する主なスズメバチの種類は以下の通りです。
オオスズメバチ

世界最大のスズメバチ。攻撃性・毒性ともに最強クラス。
主な営巣場所:地中、朽木の根元、樹洞など
キイロスズメバチ

人家周辺にも巣を作る。攻撃性・繁殖力が非常に高い
主な営巣場所:軒下、屋根裏、戸袋、樹木など
コガタスズメバチ

見た目はオオスズメバチに似るがやや小型。比較的穏やか
主な営巣場所:低木、軒下、樹木の枝など
モンスズメバチ

黒っぽい体色。夜間活動することもある
主な営巣場所:樹洞、人工構造物の隙間など
チャイロスズメバチ

他種の巣を乗っ取って営巣する。体が茶褐色
主な営巣場所:屋根裏や壁の中などの閉鎖空間
ツマグロスズメバチ
近年日本に侵入・拡大中の外来種。特定外来生物に指定
主な営巣場所:樹洞や建物の隙間など
ツマアカスズメバチ
侵略的外来種。高い繁殖力と攻撃性を持ち、養蜂への被害が深刻
主な営巣場所:樹木、建物の軒下や天井裏など
ヒメスズメバチ

比較的大型だが穏やかな性格。人を襲うケースは少ない
主な営巣場所:樹洞、屋根裏、地中など
クロスズメバチ

小型でおとなしいが、毒性は強め。衛生面にも注意が必要
主な営巣場所:地中、庭の片隅、古い建物の隙間など
キイロスズメバチの巣の特徴
キイロスズメバチの巣は、軒下や庭木、屋根裏、戸袋など人家近くに作られる例が多いと報告されています。


外観は球形からひょうたん形で、灰褐色の縞模様が層状に重なる見た目が目印とされています。夏から秋にかけて巣が拡大しやすく、働き蜂の数が増えるにつれて防衛行動が強まる傾向があると案内されています。
営巣位置が人の動線に近い場合、音や振動の影響を受けやすいと考えられます。洗濯物を干す、窓を開閉する、庭の剪定をするなど日常作業が刺激となる場合があるため、発見後は動線の一時変更が推奨されることがあります。
活動時間帯は日中が中心といわれ、夕刻には出入りが落ち着くことが多いとされています。
オオスズメバチの巣の特徴
オオスズメバチの巣は、地中や樹洞、土手の斜面、朽木の根元などに作られる例が目立つとされています。人家近くでも法面や生け垣の根元など見つけにくい場所を選ぶことが多く、直接巣を探すよりも蜂の飛行経路を追う方法が紹介されています。
花や樹液、狩り場から一直線に帰巣する動きが見られ、同じ方向に力強い飛行が繰り返される場合、巣の位置がその延長線上にあると推測されます。


地中巣では出入り口が小さく、周囲の土が踏み固められている様子が手がかりになるとされます。強い警戒音や低い羽音、周囲を旋回する行動が見られた場合は、危険が高いサインとされ、距離を広く取る判断が求められます。
林道や里山で遭遇したときは、背を向けて走らず、姿勢を低くして静かに離れる方法が推奨されることがあります。
その他のスズメバチの巣
スズメバチの種類ごとに巣の特徴は大きく異なります。以下に、日本でよく見られるスズメバチそれぞれの「巣の形状・材質・営巣場所・見分け方のポイント」を整理した表と、あわせて見分け方の詳しい解説をお伝えします。
| スズメバチの種類 | 巣の形状・材質 | 主な営巣場所 | 見分け方のポイント |
|---|---|---|---|
| コガタスズメバチ | 丸いが小ぶり。縞模様は比較的地味 | 軒下、木の枝 | 小型のボール状。巣口が底部にある |
| モンスズメバチ | 不規則な形、黒っぽい色味 | 建物の隙間、倉庫の壁内 | 巣の外観は目立ちにくく不規則なフォルム |
| チャイロスズメバチ | 他種の巣を乗っ取るため形は様々 | 屋根裏、壁の中 | 他種の巣に似るが、中の個体が茶色っぽい |
| ツマグロスズメバチ | 小型で不規則、灰色系 | 樹洞、軒下 | 巣材が薄くもろく見える。小さめの楕円型 |
| ツマグロスズメバチ | 大型、球状または壺型 | 樹上、高所の枝など | 高所に大きな球形巣。底部に目立つ巣口あり |
| ヒメスズメバチ | 地中、朽木の隙間 | 地中、朽木の隙間 | 表面が粗く、完全には覆われないこともある |
| クロスズメバチ | 小型で目立たない紙製 | 地中、古い建物の隙間 | 巣口は小さく目立たない。複数出入口がある場合も |
巣の見分け方のポイント
- 地中タイプ(オオスズメバチ、ヒメスズメバチ、クロスズメバチ):地上からはほとんど見えず、出入りするスズメバチの動きが手がかりになります。
- 高所タイプ(キイロスズメバチ、ツマアカスズメバチ):軒下や木の上など人目につく場所に営巣しやすく、巣が視認できるケースが多いです。
- ボール型の球状巣:コガタスズメバチやキイロスズメバチに多く見られます。縞模様の色の濃さや巣の大きさが判断材料になります。
- 壺型・不規則型の巣:ツマアカスズメバチのように外来種では特徴的な壺型を作る場合もあります。モンスズメバチは逆にかなり不規則な形をしています。
- 底部に巣口:キイロスズメバチ、ツマアカスズメバチなどの巣は底に大きく開いた出入り口があるのが特徴です。
- 側面や複数の巣口:クロスズメバチやモンスズメバチでは、出入り口が複数あり、構造がやや複雑なことがあります。
- キイロスズメバチは短期間で急成長し巨大化します。初期はピンポン玉ほどでも、夏後半にはバスケットボール大になることもあります。
スズメバチの種類の見分け方②巣の対処
- 季節ごとの巣の拡大スピード
- 蜂を刺激しないために
- 巣を発見したらどうする?
- 自力駆除が出来る?判断基準は?
- 初期のスズメバチの巣を自分で除去する方法
季節ごとの巣の拡大スピード
スズメバチの巣は、季節の移り変わりに伴って拡大スピードが大きく変化します。特に初夏から秋にかけての成長段階では、驚くほどの勢いで巣が巨大化するため、注意が必要です。
以下では、春・夏・秋それぞれの時期における巣の成長の特徴や、発見・対処のタイミングについて詳しく解説します。
春(4月〜6月):女王バチによる単独営巣の時期

春先は、冬眠から目覚めた女王バチが1匹で新たな巣作りを始める時期です。この時期に作られる巣は、初期巣と呼ばれ、大きさは直径5〜10cm程度の小規模なものです。
営巣場所は、人目につきにくい軒下の隅や庭木の枝先、倉庫の奥などが多く、発見が難しい傾向にあります。
この段階での駆除が最も安全かつ効果的であり、女王バチ1匹を排除するだけでその年の巣を根絶できるため、自治体によっては無料で対応してくれる場合もあります。
地域によって対応が異なるため、詳しくは市町村の公式サイトを確認することをおすすめします。
夏(7月〜8月):働きバチの増加に伴う急成長期

夏に入ると、女王バチが産卵した卵から次々と働きバチが羽化し、巣の成長は加速度的に進みます。
この段階では、巣の大きさが直径30cm〜50cm以上にまで成長することも珍しくありません。キイロスズメバチやツマアカスズメバチなどは特にこの時期の成長速度が速く、わずか数週間で巣のサイズが倍以上に膨れ上がることもあります。
また、巣の内部では1,000匹以上の個体が活動していることもあり、少しの刺激で集団攻撃を受ける危険性が高まります。夏季の巣の駆除は極めて危険を伴うため、必ず専門業者への依頼が必要です。
このような巣の成長パターンは、気温や湿度、地域の植生などによっても左右されることがわかっています。農研機構の研究でも、都市部よりも森林周辺のほうが営巣数や成長速度が顕著に高い傾向があることが示されています。
秋(9月〜10月):最大規模に達し攻撃性もピークに

秋になると巣の規模は年間で最も大きくなり、直径60cmを超えるものや、内部に3,000匹以上の個体を抱える巨大巣も確認されています。特にこの時期は、働きバチが女王や幼虫を守るための防衛本能が高まり、わずかな振動や気配に対しても敏感に反応します。
この段階の巣は極めて攻撃性が高く、過去には住宅の外壁内部にあった巣を業者が駆除中、近隣住民にも被害が及ぶという事例も発生しています。自治体によっては、9月以降の巣の駆除には「安全管理計画書」の提出や、消防署の立ち合いが必要となる地域もあります。
また、秋の終わりには巣の機能が停止し、働きバチや女王バチも次第に寿命を迎えますが、自然崩壊を待つのは推奨されません。空き家や軒下に放置された巣には翌年別の女王バチが再利用することもあるため、必ず撤去処理を行う必要があります。
季節ごとの巣の成長速度を把握しておくことは、適切な対策を講じるうえで非常に重要です。特に春先の「初期巣」発見がその後の被害リスクを大きく下げる鍵となるため、定期的な目視チェックや営巣しやすい場所の点検を習慣づけることが望まれます。
蜂を刺激しないために
スズメバチやアシナガバチといった攻撃性の高い蜂は、特定の行動やにおい、音などに非常に敏感に反応することが知られています。これらの蜂は巣を守る本能が強く、特に巣に近づく人間を「敵」とみなす可能性があります。蜂による被害を防ぐためには、蜂を刺激しないよう慎重に行動することが最も重要です。
たとえば、蜂の巣がある可能性のある場所(軒下、庭木の枝、物置など)を調査する際は、以下のようなポイントに注意を払いましょう。
音や振動に注意する
蜂は小さな音や振動にも敏感に反応する習性があります。草刈機や掃除機、電動工具などの騒音が巣の近くで発生すると、蜂は巣を攻撃されたと誤認し、集団で攻撃してくることがあります。静かな足取りを意識し、蜂の気配を感じたらすぐにその場を離れるようにしてください。
黒い服装や香水は避ける
黒や濃い色の服は、蜂にとって「敵対的な存在」と認識されやすいと言われています。また、香水や整髪料、柔軟剤などの強い香りも蜂を刺激する可能性があるため、屋外活動の際は無香料かつ白や淡い色の服装が望ましいとされています。
手で払わずに静かに離れる
蜂が近づいてきたときに反射的に手で払ってしまうのは危険です。蜂は素早い動きや攻撃的なジェスチャーに過敏に反応するため、余計に興奮させてしまうことになります。蜂が体に止まっても無理に振り払わず、ゆっくりとその場から立ち去るようにしましょう。
巣に近づかない・近寄らない
スズメバチの巣に不用意に近づくことは非常に危険です。巣から半径2~3メートル程度は「警戒ゾーン」とされ、この範囲に侵入すると蜂が威嚇行動を取る可能性があります。巣の存在に気づいたら、直ちに距離を取り、決して自力で撤去を試みてはいけません。
巣を発見したらどうする?
発見直後は無理に近づかず、まず人やペットを遠ざける対応が先決です。
状況が落ち着いたら、遠距離から写真を数枚残し、営巣場所やおおよその大きさ、出入りの有無、周辺の危険箇所(玄関や通路に近いか等)を記録します。
これらの情報は、自治体窓口や専門業者へ相談する際の判断材料になります。
相談先の選び方
自治体の環境衛生担当や生活安全窓口では、対応方針や民間業者の紹介、助成制度の有無などが案内されることがあります。
公式サイトによると、救急や消防の出動は原則として人身危険が切迫している場合に限られるとされています。したがって、通常は専門業者への依頼が基本線とされ、現地の規定に従うことが求められます。
連絡時に伝える要点
住所や正確な位置、巣の見た目と大きさの目安、種類の推定(不明でも可)、人の動線との距離、写真の有無、実施希望時期などを整理しておくと見積もりや日程がスムーズに進みます。これらのことから、記録と共有の質が安全で迅速な対処の鍵になります。
自力駆除が出来る?判断基準は?
スズメバチの巣を発見した際、まず検討すべきは「自力で駆除が可能かどうか」です。
しかしながら、その判断にはいくつかの重要な要素が関係します。駆除作業は場合によっては重大な事故につながるリスクがあるため、冷静かつ客観的に状況を評価することが必要です。
判断基準1:巣の規模と時期
巣の大きさは駆除可能性を左右する最大の要因です。
判断基準2:巣の設置場所
巣の位置も、自力駆除の成否に大きく影響します。たとえば、
- 軒下や庭木の低い位置など、手が届きやすい開放空間にある巣
- 住宅の壁面や物置の内部など、接近するのに物理的な障害が少ない場所
これらであれば、自力での作業が現実的なケースもあります。
反対に、
- 屋根裏や天井裏などの閉鎖空間
- 電柱・樹木の高所(2メートル以上)
- アパートの共用部や隣地境界近くの巣
といったケースでは、落下や二次被害のリスクが高く、自力駆除は避けるべきです。特に高所作業は転倒事故の危険も伴うため、専門知識のない一般の方が手を出すべきではありません。
判断基準3:使用できる装備と知識の有無
市販のスズメバチ用殺虫スプレーや防護服、防蜂ネットなど、最低限の装備が用意できるかも重要です。防護服がないまま作業を行うと、想定外の攻撃に対処できず、刺傷やアナフィラキシーショックといった深刻な健康被害を招く可能性があります。
自治体によっては防護服の貸し出しを行っている場合もあるので一度相談してみましょう。
自宅などにできたはちの巣を御自身で駆除するときに、はちに刺されないように防護服の貸し出しをしています。
引用:神奈川県川崎市 ハチの巣駆除用防護服の貸出し
また、スプレーの使い方や作業手順など、蜂の習性に基づいた基本的な知識があるかどうかも、自力駆除の成否を分ける要素です。
判断基準4:自身および周囲の安全確保
過去にハチに刺されたことがあり、強いアレルギー反応(アナフィラキシーショック)を経験したことのある方は、たとえ小さな巣でも自力での対応は絶対に避けるべきです。
また、乳幼児や高齢者、ペットなどが近くにいる場合は、万が一に備えて専門家による安全な処置が望まれます。
さらに、都市部の住宅密集地などでは、蜂が駆除作業中に飛散し、近隣住民に危害を加えるリスクもあります。巣の規模にかかわらず、自身と周囲の環境を総合的に判断することが求められます。
自治体や専門業者への相談も選択肢に
多くの自治体では、住民の安全確保を目的として、スズメバチの巣の駆除に関する相談窓口を設けています。中には、無料または一部助成金を活用して専門業者を手配してくれる地域もあります。
無料駆除または市の委託で実質無料制度がある自治体(例)
自治体ごとの「スズメバチの巣を無料で駆除してくれる制度」の情報は、公的な一次情報源では限定的かつ変動しやすいため、最新情報は自治体の公式サイトでの確認が必須ですが、現在判明している代表的な自治体・制度を以下に整理します。(2025年9月13日現在の情報です。)
| 自治体 | 制度内容 | 条件・対象範囲 |
|---|---|---|
| 群馬県 伊勢崎市 | 市が委託した業者によるスズメバチの巣の駆除を無料で実施 | 建物所有者・管理者等が対象(賃貸等は管理会社を通すなど条件あり) |
| 愛知県 岡崎市 | スズメバチの巣を市の委託業者が無料で駆除 | 市内の建物所有者または管理者が対象 |
| 東京都 世田谷区 | 対象の蜂の巣(キイロスズメバチ・コガタスズメバチ・アシナガバチ等)で、居住者が自力で駆除できない場合に委託業者が無料で駆除 | 高さ3メートル以内など場所・蜂の種類に制限あり |
| 埼玉県 さいたま市 | スズメバチの巣の駆除を市が無料で対応 | 自己所有または賃貸の戸建て住宅等、居住実態があることなど条件あり |
| 千葉県 松戸市 | スズメバチ等の危険蜂の巣について無料駆除を市役所で行う | 対象蜂の種類や巣の場所によって条件あり |
判断に迷った場合は、まず自治体の環境課や防災担当窓口に相談し、対応可能かどうかを確認するとよいでしょう。特に都市部や山間部では対応方針が大きく異なることもあるため、地域ごとの情報収集が重要です。
冷静な判断と準備の有無によって、自力駆除が可能かどうかは大きく左右されます。無理をせず、常に最も安全な選択肢を優先しましょう。
初期のスズメバチの巣を自分で除去する方法
巣が作られて間もない時期で、働き蜂の数が少ない場合には、適切な安全対策を講じたうえで自力で除去することも可能です。ただし、スズメバチは非常に攻撃性が高く、時には命に関わる重篤な症状を引き起こすこともあるため、状況判断と慎重な対応が何よりも重要です。
初期の巣とはどのような状態か

スズメバチの巣の初期段階とは、女王蜂が単独で巣を作り始めたばかりの状態を指します。この時期の巣はゴルフボールからテニスボール程度の大きさで、外側の層が薄く、個体数も1~数匹程度と非常に少ないのが特徴です。
4月から6月初旬がこの「初期巣」の典型的な時期に該当し、それ以降になると働き蜂が増え、巣の防衛本能が強くなっていきます。
除去作業を行う適切な時間帯
巣の除去は、蜂の活動が最も低下する「日没から数時間後」に行うのが最も安全です。特に夜間は蜂が巣の中で休んでおり、行動範囲が限定されているため、不意の攻撃を受けにくくなります。
また、外に出ていた蜂も戻って来ているため一網打尽に出来、外から戻ってきた蜂に攻撃されるリスクも減らすことが出来ます。
ただし、暗闇での作業は危険を伴うため、赤色LEDライトなど蜂に刺激を与えにくい光源を使用するのが望ましいです。
しかし女王バチ一匹しか居ない小さな巣であれば日中に行っても危険は少ないでしょう。
除去に必要な装備と道具
自力で除去する場合は、次のような装備が必要です。
・頭部・顔・首元を完全に覆う防護ネットまたは防蜂帽
・厚手の長袖・長ズボン・手袋(可能であれば防蜂スーツ)
・市販のスズメバチ専用殺虫スプレー(瞬間噴射型で10m以上噴射可能なもの)
・長めの棒や火ばさみ(巣の回収用)
・大型ビニール袋(密封処理用)
これらの道具を準備し、安全を最優先に計画を立ててから作業に移りましょう。
除去手順(初期巣または安全な場合)
- 全身を防護服または厚手の衣服で完全に覆う
- 装備の隙間(首元・手首・足首)をガムテープで目張り
- 家族やペットを屋内に避難させる
- 赤色ライトで足元を照らしながら、風上からゆっくり近づく
- ライトを消す(ハチが光に向かってくるため危険)
- 巣の「出入口」を狙って噴霧
- 蜂が飛び出して来てもひるまずに落ち着いて噴霧し続ける
※薬剤が体に付くとすぐに動けなくなるため、向かってくる可能性は低い。 - 噴霧は最低でも1本使い切る意識で行う。もしスプレーが切れたらすぐに2本目も使う。
- 巣全体を袋で覆い、長柄の道具で取り付け部をカット
- 落ちた蜂は直接触らず、ホウキとちりとりで袋に入れる
- 袋の中に再度スプレーを吹きかけ、しっかり密閉し二重にする
- もし飛び去った蜂が居れば通常の白色懐中電灯を離れた場所に置く。そこに集まった蜂にスプレーをかける
- 巣があった場所に戻ってこないように、スプレーをかけておく
注意すべき危険な点
たとえ初期の巣であっても、攻撃的な女王蜂に刺されるリスクがあります。
特にアレルギー体質の方や過去にアナフィラキシーショックを経験した方は、絶対に自力での駆除を試みてはいけません。
また、働き蜂がすでに数匹でも活動している場合は、行動範囲が広がっており、巣の外にいる個体が突然戻ってくるケースも考えられます。
さらに、スズメバチの種類によっては、初期段階でも非常に攻撃的な行動を取ることがあります。安全性に少しでも不安がある場合や、自信がない場合は、迷わず自治体や専門業者への相談を優先してください。
スズメバチの巣の種類と見分け方まとめ
・巣の初期段階は小型で気づきにくく刺激を避けて観察する
・キイロスズメバチは人家近くに営巣し出入りが活発になりやすい
・オオスズメバチは地中や樹洞の巣が多く飛行経路の観察が有効
・営巣場所だけで断定せず複数の特徴を組み合わせて判断する
・写真は遠距離から全体像と設置環境を優先して記録する
・逆光を避け連写とズームで短時間に撮影しすぐ離れる
・夏後半から秋は巣の規模が最大化し防衛性が高まりやすい
・濃色の衣類や強い香りは接近を招く可能性があるため避ける
・警戒音や体当たりが見られたら静かに距離を広げて退避する
・住所位置規模写真などの情報を整理して相談先に伝える
・自治体窓口や専門業者への早期相談が安全確保の近道になる
・集合住宅や公共施設では事前の許可と周知が求められやすい
・農薬使用はラベル遵守が前提で誤用は健康被害の恐れがある
・再発防止は封鎖清掃生ゴミ管理剪定などの環境整備が鍵になる
・要するに無理をせず安全第一で計画的に対処する姿勢が重要